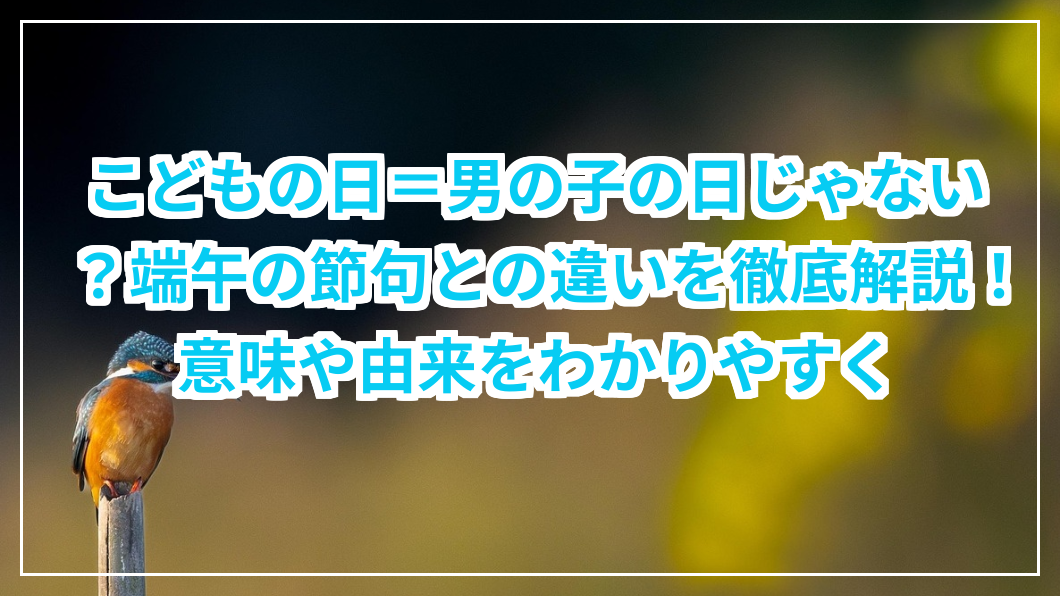「端午の節句」と「こどもの日」、どちらも5月5日だけど何が違うの?と疑問に思ったことはありませんか?実は、この二つには大きな違いがあります!端午の節句は、古くから男の子の健やかな成長を願う伝統行事。一方、こどもの日は、すべての子どもの幸福を願い、母に感謝する国民の祝日として制定されました。つまり、似ているようで成り立ちがまったく違うんです!
この記事では、「端午の節句とこどもの日の違い」をわかりやすく解説し、それぞれの由来や祝い方の違い、現代の楽しみ方まで詳しく紹介します。こどもの日のお祝い方法に悩んでいる方や、家族で楽しく過ごしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
端午の節句とこどもの日とは?基本の違いを解説
「端午の節句」と「こどもの日」、どちらも5月5日ですが、その意味は少し異なります。端午の節句は、古くから男の子の健やかな成長を願う行事として祝われてきた日本の伝統行事です。一方、こどもの日は、1948年に制定された国民の祝日で、男女を問わずすべての子どもたちをお祝いする日とされています。つまり、「端午の節句=男の子のお祝い」、「こどもの日=すべての子どもを祝う日」という違いがあるのです。
端午の節句の由来|古代中国から日本へ伝わった伝統行事
端午の節句のルーツは、古代中国にあります。中国では、5月は厄払いをする時期とされており、菖蒲(しょうぶ)を使って邪気を払う風習がありました。これが日本に伝わり、平安時代には宮中行事として定着。その後、武士の時代になると、菖蒲が「尚武(しょうぶ)=武を重んじる」という意味に通じることから、男の子の成長を祝う行事として発展しました。現在でも、こいのぼりや五月人形を飾るのは、この武士文化の名残 なのです。
こどもの日の由来|戦後に制定された国民の祝日
こどもの日は、端午の節句とは異なり、戦後に誕生した比較的新しい祝日です。1948年に日本政府が「すべての子どもの幸福を願い、母に感謝する日」として制定しました。端午の節句が男の子中心の行事だったのに対し、こどもの日は男女を問わず子ども全体のお祝いとされています。さらに、母に感謝する日とされたのは、子どもを育てる母親の努力を讃える意味が込められているからです。
端午の節句=男の子のお祝いって本当?
端午の節句といえば、男の子の成長を願う行事として知られています。これは、武士の時代に「尚武(しょうぶ)」の精神と結びつき、男の子が強くたくましく育つことを願う行事へと発展したためです。そのため、五月人形やこいのぼりを飾る風習が生まれました。しかし、現代では必ずしも男の子だけの行事ではなくなり、「家族みんなで楽しむ日」として考える家庭も増えています。
こどもの日は男の子も女の子もお祝いする日
一方で、こどもの日は「すべての子どもの幸福を願う日」として国民の祝日に制定されました。これは、端午の節句が男の子中心の行事だったことを考慮し、男女の区別なく祝う日を設ける目的があったとされています。現在では、こどもの日には家族でレジャーに出かけたり、子ども向けのイベントに参加するなど、自由な形でお祝いする家庭が多くなっています。
なぜ5月5日なの?日にちが同じ理由
「端午の節句」と「こどもの日」がどちらも5月5日なのは偶然ではありません。もともと、日本の五節句の一つである端午の節句が5月5日に定められていたため、こどもの日もその日と統一されました。また、5月は田植えの季節でもあり、昔は女性が田の神に仕える時期として大切にされていました。その名残として、菖蒲湯に入る風習も生まれたのです。
こいのぼりと五月人形|端午の節句の伝統的な飾り
端午の節句といえば、「こいのぼり」と「五月人形」が代表的な飾りです。こいのぼりは、中国の「鯉が滝を登り龍になる」という伝説に由来し、子どもが困難を乗り越えて立派に成長するよう願いを込めて飾られます。一方、五月人形(兜や鎧など)は、武士が戦で身を守るために着用したものを模しており、「子どもを災厄から守るお守り」 の意味が込められています。どちらも、男の子の健康と成長を願う伝統的なアイテムです。
柏餅とちまき|それぞれの意味と由来
端午の節句には、「柏餅」と「ちまき」を食べる風習があります。柏餅は、柏の木が「新しい葉が出るまで古い葉が落ちない」ことから、「家系が途絶えない=子孫繁栄」の象徴とされています。一方、ちまきは中国由来の風習で、「災厄を避ける」「厄払い」の意味を持ちます。地域によってどちらを食べるかが異なりますが、いずれも子どもの健やかな成長を願う縁起の良い食べ物です。
日本だけじゃない?海外の「こどもの日」事情
実は、「こどもの日」は日本だけでなく、世界各国にも存在します。例えば、中国では6月1日が「児童節(こどもの日)」とされ、学校が休みになることもあります。韓国では5月5日が「オリニナル(こどもの日)」で、日本と同じ日にお祝いされます。一方、アメリカでは「ナショナル・チルドレンズ・デー」として6月に祝われることが多いです。国によってお祝いの仕方は違いますが、「子どもを大切にする日」としての共通点がありますね。
端午の節句とこどもの日、どうお祝いする?
端午の節句とこどもの日、それぞれの意味を理解した上で、家庭でどのようにお祝いすればよいのでしょうか?伝統的な端午の節句では、こいのぼりや五月人形を飾る、菖蒲湯に入る、柏餅やちまきを食べる などの風習があります。一方、こどもの日は祝日ということもあり、レジャー施設へ出かけたり、子どもが喜ぶ料理を作ったりする家庭が多いです。最近では、端午の節句の伝統を取り入れつつ、こどもの日として家族で楽しむスタイル が一般的になっています。
現代ではどう違う?家庭での祝い方の変化
昔ながらの端午の節句では、武士の文化を反映した五月人形やこいのぼりが主役 でしたが、現代では「子どもの成長を祝う日」としてシンプルに楽しむ家庭も増えています。また、こどもの日として男女問わずお祝いする傾向が強くなり、家族で外食をしたり、旅行へ行ったりするのも定番になっています。最近では、マンション住まいの家庭向けに「室内用こいのぼり」や「コンパクトな五月人形」なども人気です。
こどもが喜ぶ!端午の節句&こどもの日のおすすめイベント
こどもの日には全国各地で様々なイベントが開催されます。例えば、大型こいのぼりが空を舞う「こいのぼりフェスティバル」、武将体験ができる歴史イベント、動物園や水族館の「こどもの日特別企画」などがあります。また、自宅で楽しめるものとして、「手作り兜を作る」「こいのぼりクッキーを焼く」「家族で菖蒲湯に入る」などもおすすめ。伝統を大切にしながら、子どもが楽しめる工夫を取り入れてみると、思い出に残る一日になりますよ。
まとめ:それぞれの意味を知って楽しくお祝いしよう
「端午の節句」と「こどもの日」は同じ5月5日ですが、意味や成り立ちは異なります。
- 端午の節句:古くから伝わる男の子の成長を願う伝統行事(こいのぼり・五月人形・菖蒲湯)
- こどもの日:すべての子どもの幸せを願い、母親にも感謝する祝日(レジャー・特別な食事)
近年では、端午の節句の伝統を大切にしながらも、こどもの日として家族全員で楽しむスタイルが増えています。こいのぼりや柏餅といった伝統を取り入れつつ、子どもが喜ぶイベントやレジャーを企画して、思い出に残る一日にしてみてはいかがでしょうか?