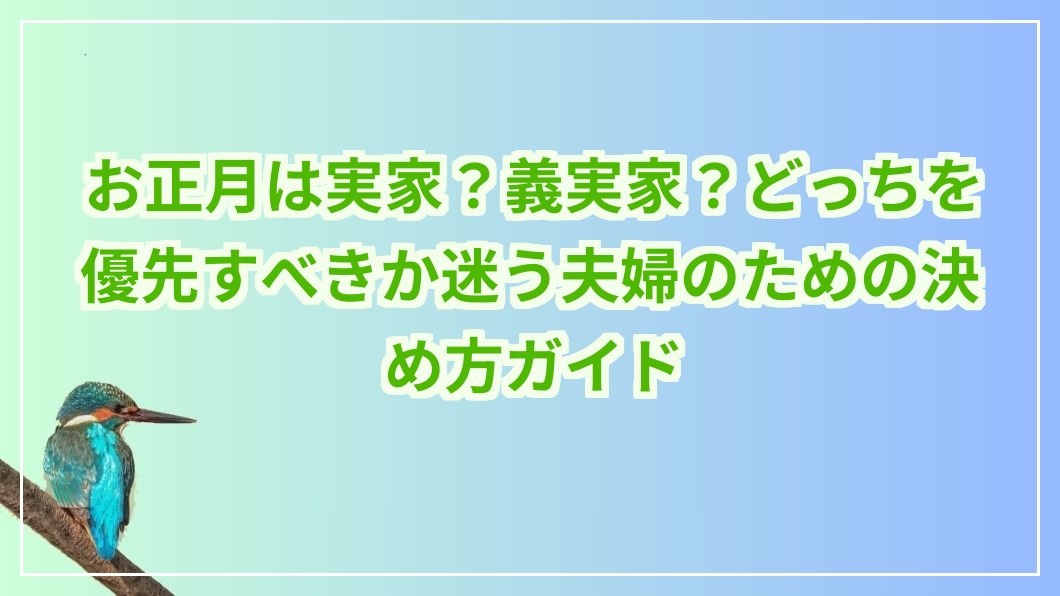お正月が近づくと、なんとなくソワソワしませんか? 「今年は実家に帰る?それとも義実家?」――その一言で、夫婦の空気がピリッと変わること、ありますよね。どちらの親にも顔を立てたいし、できれば穏やかに過ごしたい。けれど、スケジュールも子どもの予定も、親の体調も…すべてを考えると頭がこんがらがってしまう。そんな“お正月帰省ジレンマ”に毎年悩まされている人は少なくありません。
でも安心してください。この記事では、「どちらを優先すべきか」ではなく、「どうすればお互いが納得できるか」に焦点を当てて、夫婦で揉めずに決めるためのヒントをたっぷりお伝えします。読んだあとには、「もう迷わない!」「次の年末が楽しみかも」と思えるようになるはずです。あなたの家庭にぴったりな“お正月ルール”を一緒に見つけていきましょう。
お正月の「実家・義実家どっち問題」はなぜ起こるのか?
お正月が近づくたびに、「今年は実家に帰る?それとも義実家?」と夫婦で話題になる家庭は多いものです。この“どっち問題”が起こる背景には、単なる予定調整だけでなく、「公平にしたい」「どちらの親も大切にしたい」という心理が隠れています。結婚して家庭を持つと、両方の親への配慮が必要になりますが、そのバランスを取るのが意外と難しいのです。
毎年モヤモヤするのは「公平にしたい心理」から
どちらか一方を優先すると、もう一方の親に申し訳ない気持ちが芽生える…そんな経験はありませんか?特に日本では「お正月=家族で過ごす日」という価値観が根強く、両家の期待が重なりやすい時期でもあります。「去年はうちに来たから、今年は向こうへ」と交互に決めようとしても、親の体調や子どもの予定などが絡むと、なかなかスムーズにはいかないものです。
夫婦で意見が食い違う典型的なパターン
ありがちなケースとしては、「夫は自分の実家に帰りたい派」「妻は自分の実家に帰りたい派」という構図。どちらの実家も遠方であれば、移動の負担も増え、余計にストレスがたまります。中には、「どちらの親も好きなのに、毎年この話題になると気まずい」と感じている人も多いでしょう。夫婦間での意見の違いは、家庭環境や育った文化の違いから生まれることもあります。
世間の平均は?みんなはどっちに帰っている?
調査によると、夫婦での帰省先は「義実家(夫側)が多い」とされる傾向があります。特に結婚初期は、夫の実家を優先するケースが多いようです。ただし、最近では共働きや核家族化が進み、妻の実家で過ごす家庭も増えています。「どちらにも行かず、家族だけで過ごす」という選択をする夫婦も少なくありません。つまり、正解は一つではなく、“その年の状況に合わせて柔軟に決める”のが主流になってきているのです。
実家と義実家どっちを優先する?判断基準5つ
「どちらに行くべきか」を考えるとき、感情だけでなく現実的な要素も大切です。以下のようなポイントを参考にすると、納得のいく判断がしやすくなります。
距離と移動時間で現実的に決める
年末年始は交通機関が混雑し、移動だけで一苦労。遠方の実家に帰る場合は、移動時間や交通費、宿泊の有無なども考慮しましょう。たとえば「今年は近場の義実家に」「来年は長距離の実家に」といった形でバランスを取るのもおすすめです。
親の年齢や体調・介護事情を考慮する
年を重ねるにつれ、親の健康状態や介護の有無も重要な判断材料になります。特に「一人暮らしの親」「介護が必要な親」がいる場合は、優先的に会いに行くほうがよいでしょう。「今年はお義母さんの体調が心配だから義実家へ」「来年は私の母の手術後だから実家へ」といった柔軟な考え方が大切です。
子どもの年齢や過ごしやすさも大事な要素
小さな子どもがいる場合は、どちらの家で過ごすほうが快適かもポイントです。遊べるスペースや寝る環境、親戚との関係なども考えたいところ。たとえば「義実家は大人数でにぎやかだから、子どもが疲れてしまう」「実家は子ども部屋があって落ち着ける」といった違いも判断材料になります。
夫婦で揉めないための話し合い方とルール作り
どちらの実家を優先するかを決めるとき、最も大事なのは“話し合い方”です。感情的にならず、冷静に意見を出し合うことが円満のカギです。
「どっちが正しい」ではなく「どうすれば納得できるか」を話す
「私の実家のほうが…」「あなたの親が…」という言い方をしてしまうと、争いの火種になりがちです。お互いの実家を比べるのではなく、「どんな過ごし方ならお互い気持ちよくお正月を迎えられるか」を基準に考えましょう。
感情的にならないための伝え方のコツ
話し合いのときは、「あなたが悪い」ではなく「私はこう感じる」という“アイメッセージ”を使うのがおすすめです。たとえば「去年は義実家で過ごしたから、今年は自分の親にも会いたい」と、自分の希望をやわらかく伝えることで、相手も受け入れやすくなります。
“交互制”や“分担制”など柔軟なルールを決める
「偶数年は夫側、奇数年は妻側」「年末は義実家、年始は実家」など、ルールを決めておくと揉めにくくなります。状況が変われば、その都度見直してOK。あくまで「今年のベスト」を選ぶ気持ちで、柔軟に対応しましょう。
親に角が立たない「行けない理由」の伝え方
どちらかの親のもとに行けない年があるのは自然なことです。しかし、その伝え方を誤ると、思わぬ誤解やトラブルのもとになることもあります。
本音をやわらかく伝えるフレーズ例
「今年は移動が難しくて…」「子どもの予定が重なってしまって…」など、現実的な理由を添えて伝えるのがコツです。相手を責めるような言い方は避け、「本当は会いたいけれど、事情があって行けない」という気持ちを正直に伝えましょう。
義実家・実家それぞれの気持ちを立てる言い方
たとえば義実家には「毎年温かく迎えてくださってありがとうございます。今回は少し事情があって伺えませんが、また近いうちに顔を出しますね。」など、感謝の言葉を添えるだけで印象が変わります。実家には「今年は向こうの家を優先するね。でもお母さんの料理、また食べたいから春に帰るつもり」など、具体的な再会の予定を伝えると、寂しさを和らげられます。
電話・LINE・年賀状でフォローするコツ
直接会えない年でも、電話やLINE、年賀状での挨拶を欠かさないことが大切です。ビデオ通話で孫の顔を見せたり、年賀状に家族写真を添えたりするだけでも、気持ちはしっかり伝わります。
どちらの親にも気持ちが伝わるフォローアイデア
行けなかった側の親にも「大切に思っている」ことを伝える工夫をすると、関係がより良好になります。
別の時期に訪問する「ずらし帰省」
「お正月は行けないけれど、2月の連休に帰るね」など、時期をずらして訪問する方法もおすすめです。混雑を避けられるうえ、ゆっくり話せる時間も増えます。
お正月ギフト・手紙・ビデオ通話など感謝を形に
「お年賀」としてお菓子や地元の名産を贈るだけでも気持ちは伝わります。さらに、子どもの成長を写真や動画でシェアすれば、離れていても絆を感じられます。
「行かない年」でもつながりを感じる工夫
たとえば「年末にビデオ通話で一緒に乾杯」「お正月にオンライン書き初め大会」など、少しユーモアを交えた交流も素敵です。大切なのは“会えなくても関係を育てる”意識です。
まとめ:お正月は“どっちに行くか”より“どう決めるか”が大切
どちらの実家に行くかを巡って悩むのは、それだけ「どちらの親も大事にしたい」という優しい気持ちがある証拠です。完璧なバランスを取ることは難しくても、お互いの意見を尊重しながら「今年のベストな形」を見つけていくことが大切です。
家族が増えれば、事情も変わります。だからこそ、毎年少しずつ見直しながら、自分たちの“お正月ルール”を育てていきましょう。そして、どちらの家にも「思いやりの気持ち」を言葉で伝えること。それが一番の円満の秘訣です。