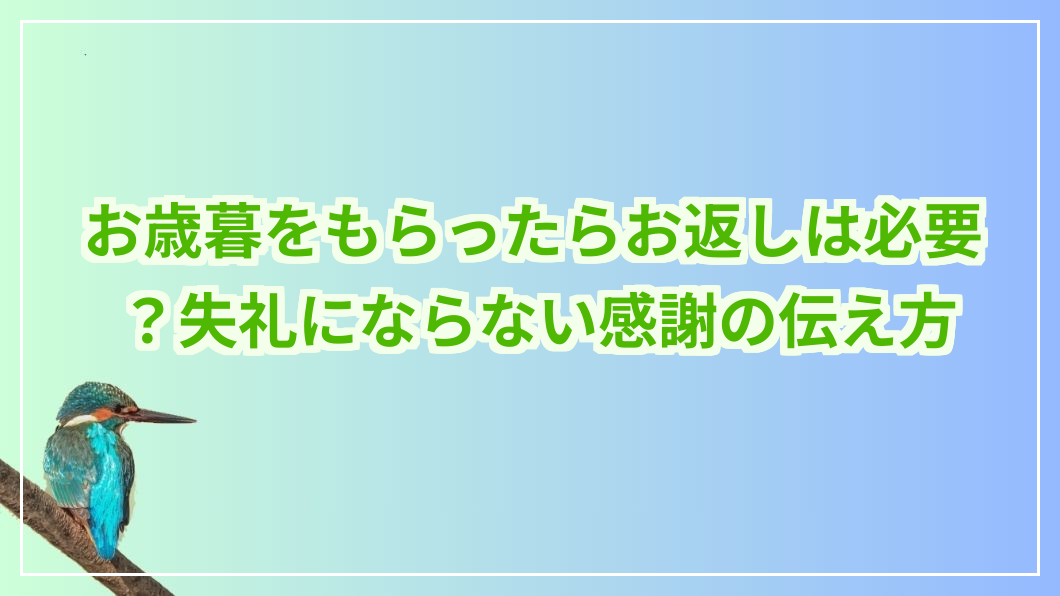年末になると、思いがけず届くお歳暮。
「わざわざ贈ってもらったけど…これ、お返ししたほうがいいの?」「しないと失礼?」と、頭を抱えたことはありませんか?
感謝の気持ちは伝えたいけれど、マナー違反になったらどうしようと不安になりますよね。
でも安心してください。実は、お歳暮のお返しには“絶対に返すべき”という決まりはなく、相手との関係性や状況によって正しい対応が変わります。
つまり、焦って返すよりも“感じの良い受け取り方”を知っておくほうが、ずっとスマートなんです。
この記事では、「お歳暮にお返ししないと失礼?」という疑問をまるごと解決し、
「返したほうがいいケース」「返さなくても良いケース」そして「感謝を伝えるベストな方法」までをわかりやすく紹介します。
読み終わるころには、「どう対応すればいいのか」がスッキリ整理され、年末のモヤモヤもきっと晴れているはずです。
お歳暮にお返ししないと失礼?まずは基本マナーを理解しよう
年末になると、お歳暮をいただく機会が増えますよね。そんなとき、「お返しをしないと失礼になるのかな?」と迷った経験はありませんか?感謝を伝えたい気持ちはあるけれど、過剰になってしまうのも心配…。実は、お歳暮のお返しには“知っておくべき基本マナー”があります。
結論|お歳暮のお返しは“原則不要”
まず知っておきたいのは、「お歳暮に対して必ずお返しをしなければならない」というルールはないということです。お歳暮は、その年にお世話になった人が“感謝の気持ちを込めて贈るもの”であり、お返しを期待して送るものではありません。ですから、無理にお返しをする必要はありません。むしろ「お心遣いをいただき、ありがとうございました」と丁寧にお礼を伝えるだけで十分です。
お歳暮は「感謝の気持ちを受け取る」側のマナー
お歳暮をいただいたときに大切なのは、「ありがたく受け取る」姿勢です。贈ってくれた人は、“感謝を伝えたい”という気持ちから贈っているのですから、笑顔で受け取り、感謝を言葉で伝えることが一番のマナーです。たとえば「お気遣いいただき、ありがとうございます」「ご丁寧に恐縮です」など、素直な言葉を添えるだけで好印象です。
無理にお返しすると逆に気を遣わせることもある
お返しをしてしまうと、「気を遣わせてしまった」と相手に思わせることがあります。特に目上の方や取引先からのお歳暮に対しては、“対等に返す”よりも、“感謝を伝える”方が正解です。もしどうしてもお礼をしたい場合は、後日お礼状を送るか、年明けに「お年賀」や「寒中見舞い」として軽くお礼をするのがおすすめです。
お返しが必要なケースと不要なケースを徹底解説
お返しが必要なケース(上司・取引先・目上の方など)
お返しが必要な場合は、相手との関係性によります。たとえば、取引先や上司など、ビジネス関係で明らかに気を遣っていただいた場合は、「今後もお付き合いを大切にしたい」という意味でお返しをするのも良いでしょう。その場合は、同額または半額程度の品を目安に選び、時期をずらして「お年賀」として贈るとスマートです。
お返しが不要なケース(親戚・友人・関係が対等な場合)
一方で、親戚や友人など、日常的に交流のある相手であれば、無理にお返しをする必要はありません。お歳暮は“感謝の気持ちの贈り合い”でもあるため、翌年にこちらから贈ることで自然なバランスを保つことができます。お返しを焦るよりも、相手の気持ちを受け取って感謝を言葉で伝える方が大切です。
“関係性”で判断するのが正解
「誰から贈られたか」「どういう関係か」を考えることが、正しいお歳暮マナーの第一歩です。形式だけにとらわれず、“気持ちのやり取り”を意識することで、相手にも好印象を与えられます。
お返しをする場合の正しいタイミングと方法
お返しは「お年賀」または「寒中見舞い」として贈る
どうしてもお返しをしたい場合は、「お年賀」または「寒中見舞い」として贈るのがおすすめです。お年賀は1月7日頃まで、寒中見舞いは1月8日から2月初旬頃までに贈るのが目安です。お歳暮として返すよりも、新年のご挨拶として贈る方が自然で、マナー違反になりません。
品物の相場は半返し〜同額程度が目安
お返しの品は、相手が負担に感じない金額を意識しましょう。一般的には、もらったお歳暮の「半額から同額程度」が目安です。たとえば、5,000円の品をいただいたなら、2,000〜3,000円程度のお菓子や紅茶、タオルセットなどが無難です。高価すぎるものは「気を遣わせる」と思われてしまうこともあるので注意が必要です。
送るときの挨拶文・メッセージのポイント
お返しを送る際は、簡単なメッセージカードやお礼状を添えるとより丁寧です。たとえば、「ご丁寧なお心遣いをいただき、誠にありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします」といった文章が好印象です。形式にこだわりすぎず、心のこもった一言を添えるのが大切です。
感謝を伝えるお礼状・メッセージ文例
ビジネス(取引先・上司)向けの文例
拝啓 歳末の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。
このたびはご丁寧なお歳暮をお贈りいただき、誠にありがとうございました。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
親戚・友人向けのカジュアルな文例
先日は素敵なお歳暮をありがとうございました。
家族みんなで美味しくいただきました。
いつもお気遣いいただき、本当に感謝しています。
寒い日が続きますが、どうぞお身体に気をつけてお過ごしください。
メールで送る場合の例文と注意点
ビジネスメールの場合は、件名を「お歳暮の御礼」として、本文で簡潔に感謝を伝えましょう。たとえば、「このたびはご丁寧なお歳暮を賜り、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。」という短い一文で十分です。メールでも、敬意を忘れないことがポイントです。
お返しをしない場合の丁寧な対応法
感謝の気持ちを言葉で伝えるだけでも十分
お返しをしない場合でも、「いただいた気持ちを大切に受け取る」ことが最も重要です。受け取った後すぐに電話やメールでお礼を伝えるだけでも、印象はぐっと良くなります。「お気遣いをいただき、ありがとうございました」と一言添えるだけで十分です。
「お気遣いなく」と辞退する際の伝え方
毎年お歳暮をいただいている場合など、「今後はお気遣いなく」とやんわり伝えたいこともあるでしょう。その場合は、「いつもお心遣いをありがとうございます。どうぞお気を遣われませんように」と柔らかい表現を使うと角が立ちません。相手に気を悪くさせない言い方を心がけましょう。
関係を悪くしない“上手な断り方”
断るときは、「感謝→辞退→気遣い」という流れで伝えるのがコツです。たとえば、「いつもお心遣いをありがとうございます。お気持ちはありがたく頂戴いたしますが、今後はどうぞご無理なさらないでくださいませ。」という言い回しが自然です。
お歳暮のお返しで失敗しないためのポイント
焦って返さない!タイミングを見極める
お歳暮をもらってすぐに慌てて返す必要はありません。年末年始は相手も忙しい時期です。まずはお礼の連絡をし、必要であれば年明けに改めて贈る方がスマートです。
品物よりも気持ちが大切
どんな高価な品よりも、「ありがとう」の気持ちを込めた一言の方が伝わります。マナーに正解はあっても、“心のこもった対応”には勝てません。
マナーを知って“感じの良い対応”を心がけよう
お歳暮のお返しは義務ではありませんが、正しいマナーを知っておくことで、相手に安心感を与えられます。お返しをする・しないにかかわらず、相手を思いやる気持ちを大切にしましょう。
まとめ|お返しは義務ではなく、感謝を伝えるチャンス
「しないと失礼」ではなく「どう伝えるか」が大切
お歳暮のお返しは“義務”ではなく、“気持ちを伝える機会”です。大切なのは「お返しをするかどうか」ではなく、「どう感謝を伝えるか」。自分らしい言葉で誠意を示すことが、一番印象に残ります。
感謝の気持ちを素直に伝えることで信頼関係が深まる
お歳暮をきっかけに、相手との関係をより良くすることができます。形式にとらわれすぎず、「ありがとう」の気持ちを素直に伝えること。これが、失礼にならずに信頼を築く、一番の方法です。