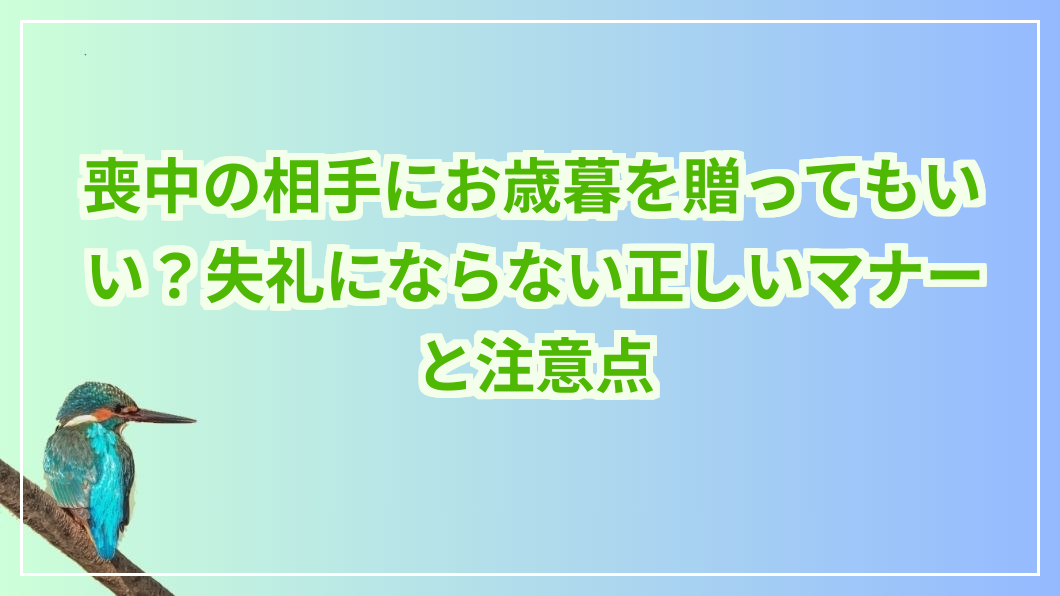毎年お歳暮の時期になると、「あの方が喪中だけど、贈ってもいいのかな…?」と迷うこと、ありませんか?
長年の付き合いだからこそ感謝を伝えたいけれど、「非常識だと思われたらどうしよう」「かえって気を遣わせてしまうかも」と不安になりますよね。
でも大丈夫です。お歳暮は“お祝い”ではなく“感謝”の贈り物。マナーを正しく理解すれば、喪中の相手にも失礼なく、むしろ“心のこもった一品”として喜ばれることもあります。
この記事では、喪中の相手にお歳暮を贈るときの正しい判断基準や、のし・言葉遣いなどの注意点をやさしく解説します。
読み終えるころには、「贈る・贈らない、どちらを選んでも大丈夫」と胸を張って言えるようになるはずです。
大切なのは“形より気持ち”。この記事を通して、相手に寄り添う思いやりの伝え方を一緒に見つけていきましょう。
喪中の相手にお歳暮を贈ってもいい?マナーの基本を理解しよう
年末になると、「毎年お歳暮を贈っている相手が喪中になったけれど、今年はどうすればいいの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。お歳暮は感謝の気持ちを伝える大切な習慣ですが、相手が喪中の場合は少し注意が必要です。ここでは、喪中にお歳暮を贈る際のマナーや注意点をわかりやすく解説します。
お歳暮はお祝いではないため喪中でも贈ってOK
まず最初に知っておきたいのは、「お歳暮はお祝いではない」ということです。お歳暮は“日頃の感謝を伝えるための贈り物”であり、おめでたい意味合いは含まれていません。そのため、喪中の相手に贈ってもマナー違反にはなりません。実際に、多くの方が喪中でもお歳暮を受け取っています。
ただし、相手が悲しみに暮れている時期であることを考え、華やかすぎる品物や包装は避けるなどの配慮が必要です。「相手の心情を思いやる」ことが、最も大切なマナーと言えます。
ただし“忌中期間”は避けるのがマナー
喪中と混同されやすいのが“忌中”です。忌中とは、故人が亡くなってから四十九日までの期間を指し、この間は特に慶事や贈り物を控えるのが一般的です。そのため、忌中の間にお歳暮を贈るのは避けましょう。忌明け後(四十九日以降)であれば問題ありません。
もしお歳暮の時期と忌中が重なってしまう場合は、1月中旬の「寒中見舞い」として贈る方法がおすすめです。この場合、のしも“寒中御見舞”に変えることで、相手への心遣いが伝わります。
贈らない選択も間違いではない理由
お歳暮を贈るか迷ったときは、「無理に贈らない」という選択も失礼ではありません。喪中の時期は、受け取る側もまだ気持ちの整理がついていないことがあります。そのような場合は、年明けに「寒中見舞い」として改めて感謝の気持ちを伝えると良いでしょう。
贈っても良いケース・控えるべきケースを判断しよう
忌明け後なら問題なし!時期をずらして贈るのも◎
四十九日が過ぎた後であれば、喪中でもお歳暮を贈って構いません。その際は、年末の忙しい時期を避け、12月20日頃までに届くようにしましょう。もし時期が過ぎてしまった場合は、先ほど触れた「寒中見舞い」として贈るのがおすすめです。
家族が亡くなった直後など「避けるべきケース」
忌中の期間や、相手がまだ悲しみの中にあるときは、お歳暮を控えるのがマナーです。特に故人が近親者である場合は、相手の気持ちを最優先に考えましょう。無理に贈ってしまうと、「今はそういう気分ではないのに…」と気を遣わせてしまうことがあります。
相手の気持ちを優先して判断するのが正解
マナーの正解は一つではありません。相手との関係性や状況によって柔軟に判断することが大切です。毎年お歳暮を贈っている間柄であっても、相手が喪中の年は「気持ちだけで十分」と考える方もいます。迷った場合は、共通の知人や家族を通じてさりげなく確認してみるのも良いでしょう。
喪中の相手にお歳暮を贈るときの注意点
のしは「紅白蝶結び」ではなく「無地の短冊」を使う
通常のお歳暮では「御歳暮」と書かれた紅白蝶結びののしを使いますが、喪中の場合は控えましょう。その代わりに「無地の短冊」や、「お歳暮」とだけ書かれた控えめなのしを選びます。包装紙も華やかな色ではなく、落ち着いた色合いのものを選ぶと良い印象です。
メッセージや挨拶文に“お祝い”の言葉は使わない
喪中の相手へのメッセージでは、「お祝い」「ご多幸」「お喜び」などの慶事を連想させる言葉は避けましょう。代わりに「日頃の感謝を込めて」「今年もお世話になりました」など、感謝の気持ちを中心に書くのがポイントです。形式よりも、相手への思いやりが伝わることが大切です。
品物は落ち着いた色味・内容のものを選ぶ
品物を選ぶ際は、華やかすぎるものや生花などは避け、落ち着いた雰囲気のものを選びましょう。お茶、焼き菓子、調味料、タオルなどの実用的な品が無難です。特にお茶は「香典返し」を連想させる場合があるため、できれば別の品を選ぶとより安心です。
お歳暮を贈らない場合の丁寧な伝え方
電話・手紙で「お気持ちをお察しします」と伝える
お歳暮を贈らない場合でも、何の連絡もせずに終わらせるのは避けましょう。電話や手紙で「このたびはご不幸がありましたこと、心よりお悔やみ申し上げます。どうぞお身体を大切にお過ごしください」といった一言を伝えるだけでも、十分な心遣いになります。
翌年に改めて感謝の気持ちを伝える
お歳暮を控えた場合は、翌年に「昨年はお世話になりました」と感謝の言葉を添えて贈るのが自然です。その際、「ご服喪中につき昨年は控えさせていただきました」と一言添えると、誠実な印象になります。
「辞退の連絡」を受けた場合の正しい対応法
喪中を理由に「お歳暮はご遠慮します」と連絡を受けた場合は、無理に贈らないようにしましょう。その代わりに、「お気遣いありがとうございました」「お気持ちだけで十分嬉しく存じます」と返信し、相手の意向を尊重するのが大人の対応です。
喪中の相手に贈る挨拶文・手紙文例集
一般的な取引先向け文例
拝啓 歳末の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
このたびはご不幸があったと伺い、心よりお悔やみ申し上げます。
日頃のご厚情に感謝の気持ちを込め、心ばかりの品をお贈りいたしました。
ご多忙の折恐縮ですが、ご笑納いただければ幸いです。
敬具
親しい知人・友人向け文例
このたびはご不幸があったとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。
日頃の感謝の気持ちを込めて、ささやかではありますが品をお贈りします。
寒い日が続きますが、どうぞお身体を大切にお過ごしください。
メールやカードで送る場合の書き方例
件名:「お歳暮のご挨拶」
本文:このたびはご不幸があったと伺い、お悔やみ申し上げます。
日頃のご厚意への感謝を込め、心ばかりの品をお送りいたしました。
今後とも変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
喪中マナーで気をつけたい言葉・表現NG集
「お祝い」「ご多幸」など慶事を連想させる言葉は避ける
喪中の相手に対しては、「お祝い」や「お喜び」といった言葉を使うのは避けましょう。代わりに「感謝」「お世話になりました」「お身体をお大事に」といった穏やかな表現を選ぶのが無難です。
「ご冥福」などお悔やみの言葉も控える場面がある
特にお歳暮の挨拶文では、お悔やみの表現は簡潔にするのがマナーです。あまり重々しくなると、かえって相手を悲しませてしまうことがあります。文面では「お悔やみ申し上げます」程度にとどめましょう。
無難で上品な言い回しに言い換えるコツ
「お祝い申し上げます」→「感謝申し上げます」
「ご多幸をお祈りします」→「お健やかにお過ごしください」
このように、言葉を少し変えるだけで柔らかい印象になります。マナーは“気持ちを伝えるための工夫”と考えましょう。
まとめ|喪中でも「思いやりの伝え方」が一番大切
贈る・贈らないより“心のこもった対応”を意識しよう
お歳暮は形式ではなく、感謝の気持ちを伝えるためのものです。喪中だからといって必ずしも控えなければいけないわけではありません。相手の状況を尊重しつつ、思いやりのある対応を心がけましょう。
正しいマナーで相手に寄り添う気持ちを伝える
喪中のお歳暮対応は難しいと感じるかもしれませんが、基本は“相手を思う心”です。マナーを押し付けるのではなく、気持ちを伝える手段として上手に活用すれば、より深い信頼関係を築くことができます。