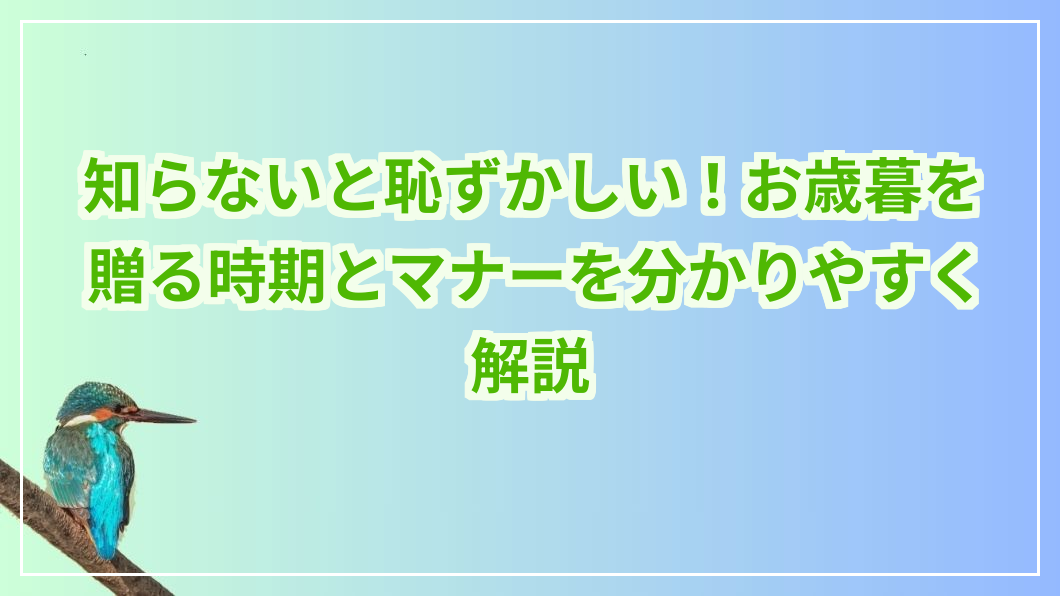年末が近づくと、そわそわしながら「お歳暮、いつ送ればいいんだっけ…?」とカレンダーを見つめていませんか?
仕事や家のことで忙しい12月、気づけばあっという間に中旬。気持ちはあるのに「今さら送っても失礼かな?」と迷ってしまう方も多いですよね。
でも大丈夫です。お歳暮の時期にはきちんとした“目安”があり、地域や相手に合わせて少し工夫すれば、遅れてもきちんと気持ちを伝えられるんです。
この記事では、「お歳暮はいつからいつまでに贈るのが正解か?」を、関東・関西の違いや遅れたときの対応法までわかりやすく紹介します。
これを読めば、「もう焦らなくていい!」とスッキリした気持ちでお歳暮の準備を進められるはず。
感謝の気持ちをスマートに伝える“時期とマナーの完全ガイド”として、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
お歳暮の時期はいつからいつまで?全国の一般的な目安
お歳暮を贈る時期は、感謝の気持ちを込める大切なタイミングです。しかし、地域や相手によって時期が少し異なるため、「いつ送ればいいの?」と迷う人も多いでしょう。基本的にお歳暮は、12月初旬から12月20日頃までに届くようにするのが目安とされています。
お歳暮の基本期間は「12月初旬〜12月20日頃」
お歳暮は、その年にお世話になった人へ「一年間ありがとうございました」という気持ちを形にする贈り物です。多くの地域では、12月初旬から12月20日ごろまでに相手の手元に届くように手配します。年末ギリギリに届くと、年越し準備などで忙しい時期に重なってしまうため、やや早めを意識するのがマナーです。
地域別で違うお歳暮の時期(関東・関西の違い)
実はお歳暮の時期には地域差があります。関東では12月初旬から20日ごろまでが一般的ですが、関西では「正月準備に入る12月13日から31日まで」が目安とされています。これは、関西では旧暦の風習が色濃く残っているためです。自分が住む地域ではなく、相手の地域に合わせて時期を決めるのがポイントです。
お歳暮を贈るベストタイミングと注意点
お歳暮の理想的なタイミングは「12月10日ごろ」。この頃に届くようにすれば、混雑を避けつつスマートに贈れます。ただし、配送が集中するため、11月下旬には手配を完了しておくのが安心です。もし遅れてしまう場合は、相手への気遣いを忘れず、のしの表書きを「お年賀」または「寒中御見舞」に切り替えましょう。
関東と関西で違う!お歳暮を贈る時期の違いを解説
関東は「12月初旬〜12月20日」がおすすめ
関東では、年末に向けて早めにお歳暮を贈るのが一般的です。特に企業間の取引先や上司へ贈る場合、12月15日までに届くようにすると印象が良いでしょう。忙しくなる前の落ち着いた時期に届くことで、相手も丁寧に受け取ることができます。
関西は「12月13日〜12月31日」までが一般的
一方で関西では、12月13日の「すす払い」以降に贈るのが昔からの習慣です。すす払いとは、神社や寺などで新年を迎えるために清めを行う行事のこと。関西ではこの日を境に「お正月準備期間」に入るため、この日以降に贈るのが礼儀正しいとされています。ただし、年末ギリギリだと慌ただしくなるため、20日ごろまでには届けたいですね。
相手が遠方の場合の発送タイミング
相手が遠方に住んでいる場合は、地域ごとの配送日数も考慮しましょう。北海道や九州などは、関東からだと到着までに数日かかることがあります。12月上旬には発送を済ませておくのがベストです。また、配送業者も年末は混雑するため、早めの準備が安心です。
お歳暮が遅れたときはどうする?代替マナーと対応法
年末を過ぎたら「お年賀」または「寒中見舞い」に切り替える
もし12月下旬を過ぎてしまった場合、お歳暮として送るのは避けましょう。新年を迎えた後に贈る場合は「お年賀」として1月7日頃までに届けるのがマナーです。それ以降になってしまった場合は、「寒中御見舞」として贈るのが正しい対応です。表書きを変えるだけで、失礼にならずに気持ちを伝えられます。
遅れた理由の伝え方・お詫び文例
お歳暮が遅れた場合は、ひとことお詫びを添えるのが大切です。たとえば「年末のご挨拶が遅くなり申し訳ございません。今年も大変お世話になりました。」という一言を添えるだけでも、丁寧な印象になります。形式的ではなく、感謝の気持ちを込めて伝えることが何より大切です。
贈り物は変えるべき?タイミング別のマナー
遅れて贈る場合でも、基本的にはお歳暮用に選んだ品で問題ありません。ただし「お年賀」や「寒中御見舞」として贈る場合は、お正月らしいお菓子や日持ちする食品に変更するのもおすすめです。時期に合った品を選ぶことで、相手への心遣いが伝わります。
贈る相手別・お歳暮の時期とタイミングのコツ
上司や取引先へのお歳暮は「早めの12月上旬」が安心
ビジネスシーンでは、礼儀を重んじる文化が根付いています。特に上司や取引先には、12月10日ごろまでに届くように手配するのがスマートです。職場で受け取る場合は平日の午前中着にするなど、相手の都合も考慮するとさらに好印象です。
親戚・友人には「年内に届けばOK」
親しい間柄であれば、多少時期が前後しても問題ありません。年末の忙しさを避けるために、12月中旬ごろに届くようにするのがちょうどよいタイミングです。相手が旅行や帰省で不在になる場合もあるため、連絡を入れてから贈ると安心です。
義実家や両親への贈り方・配送タイミング
義実家や両親など、身内に贈る場合は「直接渡す」か「配送する」かを考えましょう。帰省の予定がある場合は、持参するのも喜ばれます。遠方なら12月10日頃に届くように発送しておくとよいでしょう。手紙を添えるとより温かい印象になります。
お歳暮の準備スケジュールと失敗しない進め方
11月中に決めたい「贈るリストと予算」
スムーズにお歳暮を贈るには、11月中に「誰に」「何を」贈るかを決めておくのが理想です。リストアップしておくことで、漏れやダブりを防げます。予算は一般的に3,000円〜5,000円が目安ですが、上司や取引先には少し高めの品を選ぶと良いでしょう。
配送手配はいつまでに?混雑回避のコツ
配送業者は12月中旬から一気に混み合います。12月10日を過ぎると、希望日に届かない可能性も。早めに注文し、配送日時を指定しておくと安心です。オンラインショップを利用する場合も、在庫切れに注意しましょう。
手渡しする場合のベストタイミング
手渡しでお歳暮を渡す場合は、相手が落ち着いている時間帯を選ぶことが大切です。職場なら始業前や昼休み、訪問先ならアポイントを取ってから伺うのがマナーです。手渡しの際は、「今年もお世話になりました」と感謝の言葉を添えるのを忘れずに。
お歳暮のマナーQ&A:よくある疑問を解決
お歳暮とお中元の違いは?
お歳暮は「一年間の感謝」を伝える贈り物であるのに対し、お中元は「半年間のお礼」です。お歳暮は年末のご挨拶として定着しており、特に目上の人に贈る文化が根強く残っています。両方を贈る場合は、相手への感謝を継続して伝える意味があります。
喪中の相手にお歳暮を贈ってもいい?
喪中の相手にもお歳暮を贈って構いません。ただし、「お祝い」ではないため、のし紙の表書きを「御歳暮」ではなく「御供」とする場合もあります。包装を控えめにするなど、気遣いのある贈り方を意識しましょう。
贈るのをやめたいときの角の立たない方法
毎年お歳暮を続けていると、「もうやめたい」と思うこともあるでしょう。その場合は、徐々にフェードアウトするのが自然です。まずは品物の金額を少しずつ下げ、次の年からは年賀状で感謝の言葉を伝えるなど、相手に違和感を与えない方法がおすすめです。
まとめ|時期を守って、感謝の気持ちをスマートに伝えよう
地域・相手に合わせたお歳暮の贈り方を意識
お歳暮は単なる贈り物ではなく、「感謝」を伝える大切な文化です。地域や相手によって適切な時期が異なるため、「誰に」「いつ」贈るかを意識することで、より丁寧な印象を与えられます。
時期を逃しても「心を込めた対応」が大切
もしタイミングを逃してしまっても、焦る必要はありません。お年賀や寒中見舞いなど、別の形で感謝を伝えることができます。大切なのは「思いやりの気持ち」。相手を気遣う一言があれば、どんな時期でもその温かさはきっと伝わります。