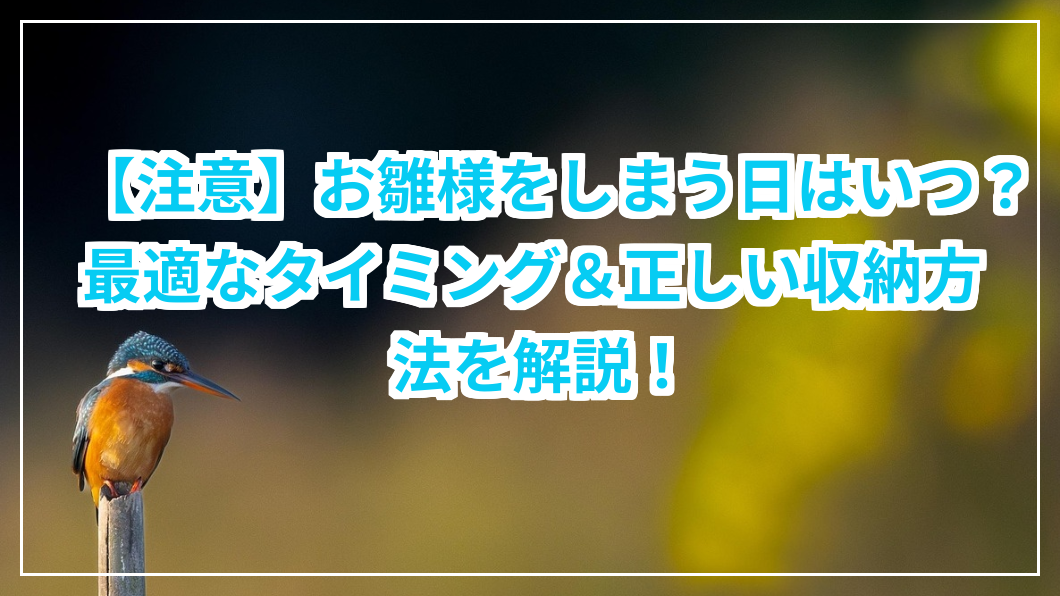ひな祭りが終わると、「お雛様、いつ片付けたらいいの?」と悩む方も多いですよね。「早くしまわないと婚期が遅れる」と聞いたことがあるかもしれませんが、それは本当なのでしょうか? また、雨の日に片付けるとカビが生えてしまうとも言われていますが、実際のところどうなのでしょう?
実は、お雛様をしまうのに最適な日は**「3月4日以降の晴れた日」**とされています。湿気の多い日に片付けると、翌年飾るときにカビやシミが発生する可能性も…。お雛様は繊細な素材でできているので、しまうタイミングや収納方法には注意が必要です。
この記事では、お雛様をしまうのにベストなタイミングや、正しい収納方法を詳しく解説します。長く美しく保つためのポイントや、片付けの際にやりがちなNG行動、先輩ママの体験談まで幅広く紹介! これを読めば、お雛様をきれいな状態で保管でき、来年も気持ちよく飾れますよ。ぜひ最後までチェックしてくださいね。
お雛様をしまう日はいつが正解?
お雛様をしまう日は、特に厳密な決まりはありませんが、一般的にはひな祭りが終わった翌日(3月4日)以降に片付けるのが良いとされています。ただし、湿気が多い日や雨の日は避け、晴れて乾燥した日を選ぶのがベスト。お雛様はデリケートな素材で作られているため、湿気を含んだまま収納すると、カビやシミの原因になることも。天気予報をチェックし、できるだけ乾燥した日に片付けるのがおすすめです。
3月3日を過ぎたらすぐに片付けるべき?
「ひな祭りが終わったらすぐに片付けないといけないの?」と悩む方も多いですよね。確かに、昔から「お雛様を早く片付けないと婚期が遅れる」という言い伝えがありますが、これはあくまでしつけの一環として広まった迷信とされています。実際には、3月3日が終わった翌日ではなく、3月中旬までに片付ける家庭も多いです。大切なのは、お雛様を丁寧に扱い、適切な方法で収納すること。慌てて片付けるのではなく、晴れた日に余裕をもって作業することを心がけましょう。
「片付けが遅れると婚期が遅れる」は本当?
「お雛様を片付けるのが遅れると、結婚が遅くなる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか? 実はこの言い伝えは、子どもに片付ける習慣を身につけさせるための教育的な意味合いで広まったもの。実際には科学的な根拠はなく、片付ける時期が多少遅れても婚期には影響しません。ただし、お雛様を長く飾りすぎるとホコリがついたり、日焼けしてしまう可能性があるため、適切なタイミングで片付けることが大切です。
お雛様をしまうのに適した天気と時間帯
お雛様を片付ける際に最も大切なのは「湿気を避けること」です。しまうのに最適なのは、晴れて乾燥した日。雨の日や湿度の高い日は、お雛様が湿気を吸い込んでしまい、収納後にカビやシミの原因になることがあります。理想的なのは、午前中から昼過ぎにかけての時間帯に片付けること。空気が乾燥している時間に作業をすることで、お雛様をきれいな状態のまま収納できます。
また、収納する前にしっかり乾燥させることも重要です。お雛様や飾り台に付いたホコリを柔らかい布で優しく拭き取り、風通しの良い場所で少しの間乾かしてから収納すると、長持ちしやすくなります。
片付ける前にやるべき準備とチェックポイント
お雛様を片付ける前に、以下の準備をしておくとスムーズに収納できます。
① 手をきれいに洗う
お雛様はデリケートな素材で作られているため、汚れや皮脂が付かないように手を洗ってから作業しましょう。
② お雛様の状態をチェックする
- 人形や道具に汚れやホコリがついていないか
- 破損している部分がないか
- ひな壇や屏風が傷んでいないか
もし汚れがある場合は、柔らかいハケや布で優しく拭き取ります。破損している場合は、専門の修理サービスに相談すると長く大切にできます。
③ 収納スペースを確保する
収納場所がホコリっぽかったり湿気が多いと、お雛様の劣化を早める原因になります。収納する前に、スペースを掃除し、除湿剤を置くと安心です。
お雛様の正しい収納方法と注意点
お雛様を長くきれいに保つためには、正しい収納方法が大切です。
① 人形は個別に包む
お雛様は繊細な素材でできているため、個別に包んで収納します。柔らかい和紙やシルクペーパーで包むのがベスト。新聞紙はインクの成分が付着してしまうため、使用しないようにしましょう。
② ひな壇や小物類も丁寧に収納
飾り台や屏風、ぼんぼりなどの小物も、壊れないようにクッション材で保護して収納します。箱に詰める際は、重いものを下に、軽いものを上に配置すると破損しにくくなります。
③ 収納場所は風通しの良い場所を選ぶ
収納場所は、湿気が少なく、直射日光が当たらない場所が最適です。押し入れやクローゼットの中にしまう場合は、除湿剤を入れて湿気対策をしましょう。
湿気・カビ対策!長く美しく保つためのコツ
お雛様は湿気やカビに弱いため、収納時の環境を整えることが重要です。適切な対策をしないと、翌年飾るときにカビやシミが発生していることも…。以下のポイントを押さえて、長く美しく保ちましょう。
① 収納前にしっかり乾燥させる
片付ける前に、柔らかい布やハケでホコリを払い、風通しの良い場所で1時間ほど陰干しすると、湿気を防げます。
② 除湿剤・乾燥剤を活用する
収納箱の中に、シリカゲルや炭入りの除湿剤を入れると湿気対策になります。ただし、人形に直接触れないよう注意しましょう。
③ 1年に1度は状態をチェック
長期間収納していると、カビや虫害が発生することもあります。年に1回、箱を開けて空気を入れ替えると、きれいな状態を維持しやすくなります。
ひな人形の収納に便利なアイテム・グッズ紹介
収納時のトラブルを防ぐために、以下のような便利なグッズを活用するのもおすすめです。
- 不織布の収納袋(通気性がよく、湿気を防ぐ)
- 桐の収納箱(湿気に強く、カビが発生しにくい)
- 防虫・防カビシート(人形や小物を包んで収納すると安心)
- 専用収納ケース(仕切りがあり、コンパクトに整理できる)
特に桐箱は、湿気や虫害からお雛様を守るのに最適な収納アイテム。押し入れやクローゼットにしまう場合は、通気性の良い不織布の収納袋を使うのもおすすめです。
片付ける際にやってはいけないNG行動
お雛様を片付けるとき、知らず知らずのうちにやってしまいがちなNG行動をチェックしておきましょう。
① 雨の日や湿気の多い日に収納する
湿度が高いと、お雛様が湿気を含んでカビの原因に。必ず晴れた日に片付けましょう。
② ビニール袋で密封する
湿気を閉じ込めてしまい、カビやシミの原因になります。通気性の良い和紙や不織布を使いましょう。
③ 新聞紙で包む
新聞紙のインクが人形や衣装に移ってしまうことがあるため、避けたほうが良いです。
④ 箱に詰め込んで押し込む
形が崩れたり、破損の原因になるため、ゆとりを持たせて収納しましょう。
これらのポイントに気をつければ、お雛様を長くきれいに保管できますよ!
お雛様をしまうときにするお供えやお清め
お雛様を片付ける前に、「今年も無事にひな祭りを終えられたこと」への感謝を込めて、お供えやお清めをする家庭もあります。特に、代々受け継がれているお雛様や、大切にしている人形の場合は、丁寧にお別れの挨拶をすることで、気持ちよくしまうことができます。
① ひな祭りのお供えを片付ける
ひなあられや菱餅などの供え物は、食べるか処分し、飾りが残らないように整理します。
② お雛様に「ありがとう」と声をかける
人形は昔から「魂が宿る」とも言われているため、軽くお辞儀をして「今年もありがとう」と声をかけると、丁寧な気持ちで片付けられます。
③ 白い紙(半紙)を敷いて清める
気になる場合は、半紙や白い布を敷いた上でお雛様を包み、心を込めてしまうのも良いでしょう。
収納スペースがない場合の保管方法と工夫
お雛様は意外と収納スペースを取るため、「しまう場所がない!」と悩むこともありますよね。そんなときは、工夫次第でコンパクトに保管することができます。
① クローゼットや押し入れの上段を活用
湿気がたまりやすい床付近ではなく、高い位置に保管するのがベスト。湿気対策として除湿剤を置くのもおすすめです。
② 収納ケースを利用する
専用のコンパクト収納ケースを活用すれば、省スペースで保管できます。桐箱タイプの収納ケースなら湿気対策もバッチリ!
③ 祖父母や親戚に預かってもらう
どうしても収納場所が確保できない場合は、実家や親戚に相談し、一時的に保管してもらうのも一つの方法です。
ひな祭りの後も飾っていい?地域ごとの違い
「お雛様は3月3日が終わったらすぐに片付けなければいけないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。実は、地域によって片付ける時期に違いがあります。
① ひな祭りが終わったらすぐに片付ける地域(関東など)
関東では、「お雛様を早めに片付けないと婚期が遅れる」という言い伝えが根強く、ひな祭りが終わるとすぐにしまう家庭が多いです。
② 旧暦のひな祭りまで飾る地域(関西・九州など)
関西や九州の一部地域では、4月3日(旧暦のひな祭り)まで飾る風習があるところも。地域の習慣によって片付ける時期が異なるため、周囲の風習を確認してみるのも良いでしょう。
どの地域でも大切なのは、お雛様をきれいに保管し、次の年も気持ちよく飾れるようにすること。地域の習慣を参考にしつつ、自分の家庭に合ったタイミングで片付けましょう。
先輩ママの体験談!片付けの失敗&成功エピソード
実際にお雛様を片付けた先輩ママたちの体験談を参考にすると、スムーズに収納できるコツが見えてきます。
失敗エピソード
- 「湿気の多い日に片付けてカビが発生!」(40代・母親)
「ひな祭りが終わった翌日が雨だったけれど、そのまま片付けてしまいました。翌年開けたら、屏風にカビが…!湿気の少ない晴れた日に片付けるのが大切だと痛感しました。」 - 「新聞紙で包んでインクが移ってしまった…」(30代・母親)
「お雛様を新聞紙で包んで保管していたら、翌年開けたときに顔や衣装にインクの跡が!ちゃんと和紙や不織布で包めばよかったと後悔しています。」
成功エピソード
- 「桐の収納箱+除湿剤でカビ知らず!」(50代・母親)
「以前、カビが気になったので、思い切って桐の収納箱に変えました。おかげで毎年きれいな状態で飾れています。除湿剤も入れるとさらに安心ですよ!」 - 「お供えをして、感謝の気持ちで片付けました」(30代・母親)
「お雛様を片付けるときに、家族みんなで『ありがとう』と声をかけて、お清めをしてから収納しました。なんだか気持ちがすっきりして、また来年も大切に飾ろうと思えました!」
まとめ
お雛様をしまう日は、ひな祭りが終わった3月4日以降の晴れた日が理想的です。
ポイント
- 片付ける時期:3月4日以降、遅くとも3月中旬までが目安
- 天気を選ぶ:雨の日や湿気の多い日はNG!乾燥した日に片付ける
- 正しい収納方法:
- 人形は和紙や不織布で個別に包む
- 小物も丁寧に収納し、桐箱や収納ケースを活用
- 除湿剤や防虫シートを入れて湿気・カビ対策をする
- NG行動に注意:
- ビニール袋や新聞紙で包まない
- 押し入れの下段など湿気の多い場所には置かない
お雛様は家族の大切な思い出の一部です。正しく片付けて、次の年も美しい状態で飾れるようにしましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました。