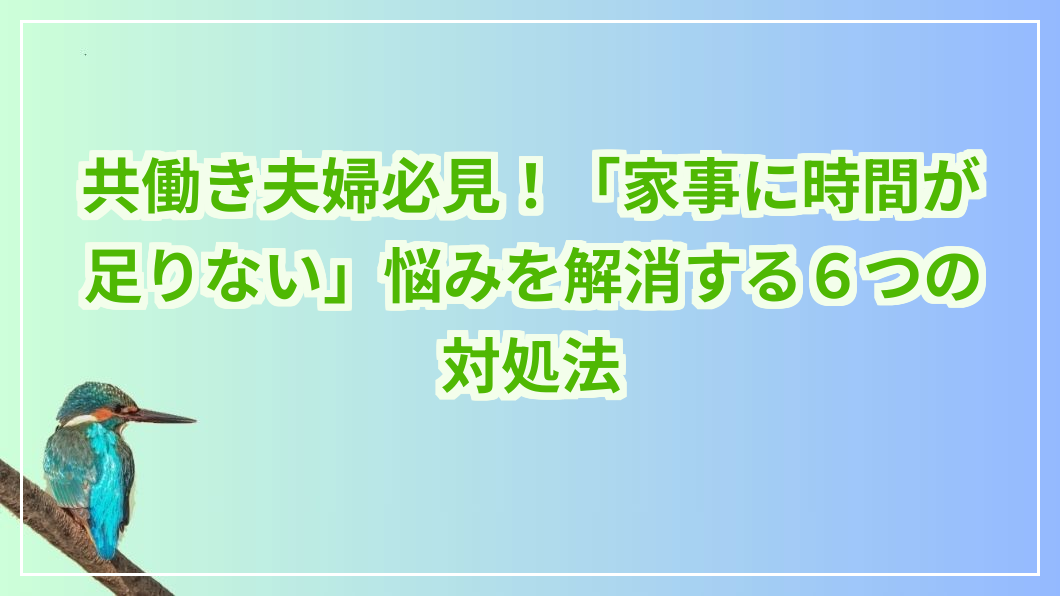朝は時間との戦い、夜は疲れとの戦い。仕事を終えて帰宅しても、洗濯物の山と冷蔵庫の中身にため息…。
「一日が24時間じゃ足りない!」と感じること、ありませんか?
共働き家庭では、家事・育児・仕事のバランスを取るだけでも大仕事。
気づけば自分の時間も夫婦の会話も後回しになってしまう。そんな“家事に追われる毎日”から抜け出したいと思うのは当然のことです。
でも大丈夫です。家事は“努力”ではなく“仕組み”でラクになります。
この記事では、共働き夫婦のリアルな悩みをもとに、今日から試せる6つの対処法を紹介します。
時間と心のゆとりを取り戻すヒントを、あなたの暮らしにお届けします。
家事に時間が足りない本当の理由
家事に追われてしまう原因は「忙しいから」だけではありません。実は、気づかぬうちに“家事の見えない部分”に多くの時間を取られていることが多いのです。
「名もなき家事」が生む見えない負担とは?
「トイレットペーパーの補充」「調味料の補充」「ゴミ袋の交換」——これらはほんの数分の作業ですが、積み重なると膨大な時間になります。これがいわゆる“名もなき家事”。しかも、誰がいつやるかが決まっていないため、気づいた人がやることになり、結果的に負担が偏ってしまうのです。
さらに厄介なのは、名もなき家事は「やっても気づかれにくい」という点。料理や掃除のように“成果が見えない”ため、達成感も少なく、「なんで私ばっかり…」という気持ちが募ってしまいます。この小さなストレスの積み重ねが、「家事がしんどい」「時間が足りない」という大きな悩みにつながっていくのです。
共働き家庭ならではの時間ギャップ—朝・夜・移動時間の使い方
共働き家庭では、夫婦それぞれの勤務時間や生活リズムが異なることも多く、「時間ギャップ」が生まれがちです。朝の支度や子どもの送迎、夜の片付けや洗濯など、どちらがどの時間帯に動けるかによって家事の偏りが生まれます。たとえば、夫が夜勤で妻が日勤の場合、生活リズムのズレが原因で家事がスムーズに回らなくなることも。
また、通勤時間が長い人ほど「物理的に家事をする時間」が少なくなるため、結果として在宅時間の長い方に家事負担が集中してしまうケースもあります。このように、時間そのものよりも“時間の使い方”に問題があることが多いのです。
まずは“見える化”する:家事負担を可視化する方法
家事における不満やストレスの多くは、「自分ばかりやっている気がする」という思い込みから生まれます。その解消に効果的なのが“見える化”です。家庭の中のタスクをすべて可視化することで、誰がどの家事を担っているのかが明確になり、冷静に話し合う土台ができます。
家事をリストアップして誰が何をしているか明らかにする
まずは家庭内で発生する家事をすべて書き出してみましょう。「料理」「洗濯」「掃除」「買い物」といった大きなカテゴリーだけでなく、「お弁当の準備」「郵便物の仕分け」「保育園の持ち物チェック」などの細かいタスクも忘れずに挙げます。
そして、それぞれの家事に「主担当」「サブ担当」を決めていきます。視覚化することで、「意外と自分に偏っているな」「ここは交代できそうだな」という気づきが得られます。家事を責め合うのではなく、チームとして協力するきっかけになるのです。
ホワイトボード・アプリ活用で家事スケジュールをルーティン化する
見える化したら、それを日々のスケジュールに落とし込むのがおすすめです。冷蔵庫の横にホワイトボードを貼って「誰が」「いつ」「何を」やるのかを書いておくだけでも、家事の抜け漏れが減ります。
最近では「Yieto」や「Tody」など、家事分担を管理できるアプリも人気です。スマホで共有できるので、在宅・出社・夜勤など働き方が異なる家庭でも活用しやすいのが魅力です。可視化とスケジュール化、この2つの掛け合わせが“家事の渋滞”を防ぐ鍵になります。
毎日の時間を少しでも生み出す時短テクニック
「時間が足りない」と感じるなら、まず“減らす工夫”をしてみましょう。家事をすべて頑張る必要はありません。仕組みと道具を上手に使えば、無理せず1日1時間の余裕を生み出すことも可能です。
「まとめ買い・作り置き・ネットスーパー」で買い物・料理を効率化
買い物の頻度を減らすことは、時間節約に直結します。週末にまとめ買いをしておくと、平日の夕方にスーパーへ寄る手間が省けます。最近はネットスーパーや食材宅配サービスが充実しており、「玄関まで届けてくれる」便利さは一度使うと手放せません。
また、休日に3日分だけでも作り置きをしておくと、平日の夕食準備がぐっと楽になります。たとえば、「鶏の照り焼き」「ひじき煮」「野菜スープ」などを冷蔵しておけば、あとは温めるだけ。朝食やお弁当にも流用できるので、二重三重に時短効果があります。
時短家電・ひと手間カットで掃除・洗濯の時間を削る
「時間がない」と嘆く前に、家電の力を借りてみましょう。食洗機、ロボット掃除機、乾燥機付き洗濯機。この3つは“共働き三種の神器”と呼ばれるほど、家事時間を短縮してくれます。
たとえば食洗機を導入すれば、1日20分、年間で約120時間の時短。ロボット掃除機が1日1回自動で掃除してくれれば、「掃除しなきゃ」というプレッシャーから解放されます。お金を時間に変えるという発想を持つことが、共働き時代の新しい家事スタイルです。
家事分担でチームになる:夫婦で動くためのルール
家事を「手伝うもの」と捉えてしまうと、どうしても負担のバランスが崩れます。大切なのは、「家事を一緒に回す」というチーム意識を持つことです。
得意・不得意を考慮した“家事マトリクス”で役割を決める
すべての家事を50:50で分ける必要はありません。お互いの得意・不得意を踏まえて役割を決める方が、結果的に効率も良くストレスも少ないです。たとえば、料理が好きな人は平日の夕食を担当し、掃除が得意な人は週末のリセットを担当するなど、自然と続けられる形にしましょう。
「苦手だけど必要な家事」については、サポートや外注を検討するのもありです。完璧を目指すより、“無理なく続く仕組み”を作ることが、夫婦円満の秘訣です。
感謝・声かけ・口出ししないルールが長く続くカギ
「ありがとう」の一言が、家事を前向きに続ける最大のエネルギーです。どちらかが頑張っているときに感謝の言葉をかけるだけで、家庭の空気は驚くほど変わります。
逆に、「そのやり方じゃダメ」と口出ししてしまうと、やる気を失わせてしまうことも。家事は“結果が同じなら手順は自由”というスタンスで、お互いを尊重することが大切です。小さな思いやりが、長期的なチームワークを支えます。
外部リソースを賢く使う:時短家電・家事代行サービス
「全部自分でやらなきゃ」と思い込む必要はありません。今は家事を外部に委ねることも立派な選択肢です。時間と心の余裕を買うつもりで、上手に取り入れてみましょう。
最初の設備投資で“毎日”がラクになる家電例
最新の家電は、共働き家庭の味方です。乾燥機付き洗濯機、食洗機、コードレス掃除機などは、初期費用こそかかりますが、長い目で見れば時間の節約効果は抜群です。1日にたった30分の時短でも、年間で180時間。これは丸7日分の自由時間に相当します。
また、最近は月額制の家電レンタルサービスも充実しています。高額な家電を試しに使ってみたい場合には、レンタルから始めるのもおすすめです。
月に1回でも使える家事代行/アウトソースの選択肢
家事代行サービスは「お金持ちの贅沢」ではなく、今や共働き家庭の定番サポートです。月に1回、2時間だけでもプロに掃除をお願いすれば、週末のストレスが格段に減ります。キッチンや浴室など、時間がかかる部分をピンポイントで頼むのも効果的です。
さらに、宅配クリーニングやミールキットの活用もおすすめです。「ご飯の献立を考える」「洗濯物を干す」といった“考える時間”を減らせば、1日の負担がかなり軽くなります。外注をうまく使うことは、家族全員が笑顔でいられる時間を増やす投資でもあるのです。
続けられる仕組みとマインド:完璧主義を手放してゆとりをつくる
最後に、家事をラクにする最大のポイントは「完璧を目指さない」ことです。100点を目指すより、70点で続けられる方法を探すほうがずっと現実的です。
「できたこと」に目を向ける“加点方式”でストレス軽減
家事は終わりのない仕事です。「あれもできてない」「これも忘れた」と減点思考になると、疲れが倍増します。そこで意識したいのが、“できたこと”に目を向ける加点方式。今日は洗濯を回せた、朝ごはんをちゃんと作れた——それだけで十分です。
少しでも前に進んでいる自分を認めることが、ストレスを溜めないコツ。完璧を目指すより、「まあいっか」と笑える心の余裕が、家事を続ける原動力になります。
話し合いやルールの見直しで、家事は変えていけるものと知る
家事の分担やルールは、一度決めたら終わりではありません。子どもの成長や働き方の変化によって、必要な見直しは必ず出てきます。たとえば「子どもが小学生になったから、お風呂掃除はお願いしよう」「在宅勤務が増えたから朝の家事は私が担当する」など、柔軟に更新していくのが理想です。
家事は“変えられるもの”という前提を持てば、心もずっと軽くなります。大切なのは、「無理せず続けられる家事」を夫婦で一緒に模索していくこと。完璧よりも快適を目指す、それが共働き家庭の新しいスタンダードです。
おわりに
家事がうまく回らないときは、自分を責めずに仕組みを見直してみましょう。見える化・時短化・分担化・外部化、そして心の余裕。この6つのステップを少しずつ取り入れていけば、きっと「前よりラクになった」と感じられるはずです。あなたの毎日に、少しでも笑顔とゆとりが増えますように。