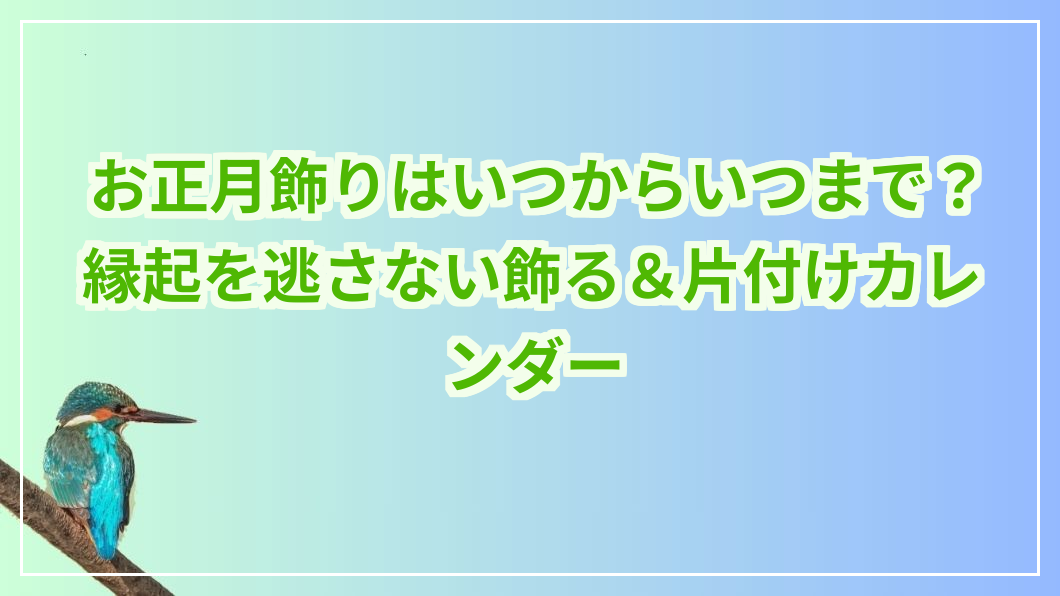年末が近づくと、「お正月飾り、いつ出すんだっけ?」とカレンダーを見ながら悩んでしまうこと、ありませんか?
クリスマスが終わると慌ただしく掃除に買い出し、気づけば大晦日。「あっ、飾るの忘れてた!」と慌てて玄関に門松を置いたり…でも実は、それ、ちょっと縁起を落とすタイミングかもしれません。
せっかく新しい年を迎えるなら、年神様をきちんとお迎えして、幸運をしっかり呼び込みたいですよね。正しい時期にお正月飾りを整えることで、家の中の空気もぐっと清々しくなり、「よし、今年もいい一年にしよう!」と心まで明るくなるものです。
この記事では、「お正月飾りはいつからいつまで飾るのが正解か?」を、わかりやすく解説します。避けたほうがいい日や地域ごとの違い、しめ縄・門松・鏡餅などの飾り別の期間、そして片付けのマナーまで、すべて一度にスッキリわかります。
読み終えるころには、「来年こそ完璧に飾れた!」と胸を張って言える自分に出会えるはずです。
お正月飾りを飾る意味とは?年神様を迎える準備
お正月飾りを準備するのは、単なる季節の風物詩ではありません。実は、お正月飾りには「年神様(としがみさま)」という新年の神様をお迎えする大切な意味が込められています。年神様は、その年の家族の幸せや健康、豊作をもたらす神様です。お正月飾りは、その神様を気持ちよくお迎えする“おもてなし”のような役割を果たしているのです。
年神様とは?お正月飾りに込められた祈り
年神様は「歳徳神(としとくじん)」とも呼ばれ、一年の幸福や恵みを授けてくれる神様とされています。お正月に家々へ降りてこられ、その家に宿るといわれています。そのため、門松やしめ縄、鏡餅といった飾りは、神様の目印や居場所を示す大切なサインなのです。たとえば門松は「神様が降りる依代(よりしろ)」であり、鏡餅は神様が宿る場所を表しています。
門松・しめ縄・鏡餅の役割の違い
門松は玄関先に立てて、年神様を迎えるための“目印”になります。しめ縄は「この先は神聖な場所です」という結界の意味を持ち、神様を迎える清らかな空間を示します。そして鏡餅は、年神様の居場所として家の中に飾られるもの。つまりこの三つがそろうことで、「神様を招き、清め、もてなす」準備が整うのです。
なぜ「飾る時期」が重要なのか
年神様をお迎えする飾りは、時期を間違えると縁起が悪いといわれます。飾る日や片付ける日には、昔からの風習や意味がしっかりと根付いているのです。「とりあえず年末に飾ればいいや」と思っていると、実は知らないうちに“縁起を逃している”こともあるかもしれません。では、具体的にいつから飾り、いつまで飾るのが正しいのでしょうか。
お正月飾りはいつから飾るのが正解?
一般的な飾り始めは12月28日がベスト
もっとも縁起の良いとされている飾り始めの日は「12月28日」です。末広がりの“八”が入っており、「末永く幸せが続く」という意味があります。この日に飾ることで、年神様を気持ちよくお迎えできる準備が整うといわれています。
避けるべき日:29日と31日の理由
逆に避けたほうがいい日が「12月29日」と「12月31日」です。29日は「二重苦」と読めることから、昔から縁起が悪いとされています。そして31日は「一夜飾り」といわれ、神様を迎える準備がたった一晩だけでは失礼にあたるとされてきました。お通夜などを連想させることもあり、避けられるのが一般的です。
地域によって違う「飾り始め」ルール
関東ではクリスマス明けの26日ごろから飾り始める家庭も多く、関西では28日を中心に準備することが多いようです。雪の多い地域では外飾りを早めに出すなど、気候によっても違いがあります。つまり、「自分の地域や家の事情に合わせて準備すること」が大切です。
お正月飾りはいつまで飾る?松の内の期間に注目
関東と関西で違う!松の内の違い
お正月飾りを片付ける目安は、「松の内(まつのうち)」と呼ばれる期間が終わる日です。関東では1月7日まで、関西では1月15日までが一般的です。松の内とは、年神様が家に滞在している期間のこと。つまり、その期間中は飾りを外さないのが正しいとされています。
片付けのタイミングを逃さないコツ
7日や15日を過ぎても飾りっぱなしにしていると、「神様をお見送りし忘れた」とされることがあります。予定が立て込むお正月明けですが、あらかじめ片付け日をカレンダーに入れておくと安心です。
飾りを外すときのマナーと注意点
飾りを外すときは、感謝の気持ちを込めて丁寧に扱いましょう。雑に外したり、ほこりまみれのまま片付けるのはNGです。神様を見送る大切な儀式ですから、「ありがとうございました」と心の中で伝えるだけでも気持ちが整います。
飾り別ガイド|しめ縄・門松・鏡餅の正しい期間
しめ縄を飾る期間と注意点
しめ縄は、年神様をお迎えするために玄関や神棚に飾るものです。飾る期間は12月28日から1月7日(または15日)までが目安です。濡れたり汚れたりした場合は取り替えを検討しましょう。紙垂(しで)が破れていたら、神様を迎える結界が弱まっているサインです。
門松はいつ立てていつ片付ける?
門松は、年神様が降りてくる“目印”として飾ります。設置は12月26〜28日ごろが理想で、片付けは松の内が終わる日です。長く置きすぎると「季節外れ」と見られることもありますが、神様を丁寧にお見送りしてから片付けるのがマナーです。
鏡餅はいつから供えていつ下げる?
鏡餅は年神様の居場所として、室内に飾ります。飾り始めは28日が理想で、下げるのは1月11日の「鏡開き」の日です。この日にお餅を割って食べることで、「神様から力をいただく」とされているんです。包丁を使わず、手や木槌で割るのが昔ながらの作法です。
お正月飾りを片付けた後の正しい処分方法
どんど焼きで清めてお焚き上げする
お正月飾りを外した後は、神社などで行われる「どんど焼き」でお焚き上げをするのが最も丁寧な方法です。火にくべることで、年神様を天にお送りし、その煙とともに幸福を祈る行事です。どんど焼きに参加できない場合は、氏神様の神社に納めても構いません。
神社への納め方・自宅処分のマナー
神社に納める場合は、受付期間やルールを確認してから持ち込みましょう。袋などに入れて持参する際は、透明の袋や紙袋を使うと丁寧です。どうしても自宅で処分する場合は、塩で清めて新聞紙に包み、感謝の気持ちを込めて捨てます。
捨てるときの縁起を守る方法
「燃えるゴミに出すなんて神様に失礼では?」と思う方もいますが、しっかり清めれば問題ありません。大切なのは“心を込めること”。形だけでなく、感謝の気持ちを持つことが何よりも重要です。
よくある質問Q&A|「飾るのが遅れたら?」「マンションでは?」
12月31日に飾るのはダメ?対処法を紹介
どうしても時間がなく、31日に飾ることになってしまった場合は、「一夜飾り」にならないよう、早朝に飾るのがおすすめです。年神様に「心を込めて準備しました」という気持ちを伝えることが大切です。焦らず、清潔に整えましょう。
マンションや玄関が狭い場合の飾り方
最近では、ミニサイズの門松やしめ縄リースなど、省スペースで飾れるアイテムも人気です。玄関ドアに貼るだけのタイプや、棚の上に置ける小さな鏡餅もおすすめ。大切なのは“形より心”。小さくても清らかな気持ちで飾れば、きっと神様も喜んでくれます。
使い回しはOK?新しい年の縁起を保つコツ
お正月飾りは基本的に毎年新しくするのが理想です。古いものを使うと、その年の穢れを持ち越すといわれています。ただし、立派な飾りで再利用したい場合は、塩で清めてから使いましょう。
まとめ|お正月飾りを正しい時期に飾って運気アップ
飾る日・片付ける日をカレンダーで再確認
お正月飾りは「いつからいつまで」がとても大切です。28日に飾って、松の内が終わる7日または15日に片付ける。このリズムを覚えておくと、毎年の準備もスムーズになります。飾るときも片付けるときも、感謝の気持ちを忘れずに行うことが、良い年を迎える一番の秘訣です。
家族みんなで気持ちよく新年を迎えよう
年末の忙しさの中でも、お正月飾りを整える時間は心を落ち着けるひとときです。家族と一緒に飾りながら、「今年も良い一年になりますように」と願う。その気持ちこそが、新しい年の運気を呼び込む最大の力になります。