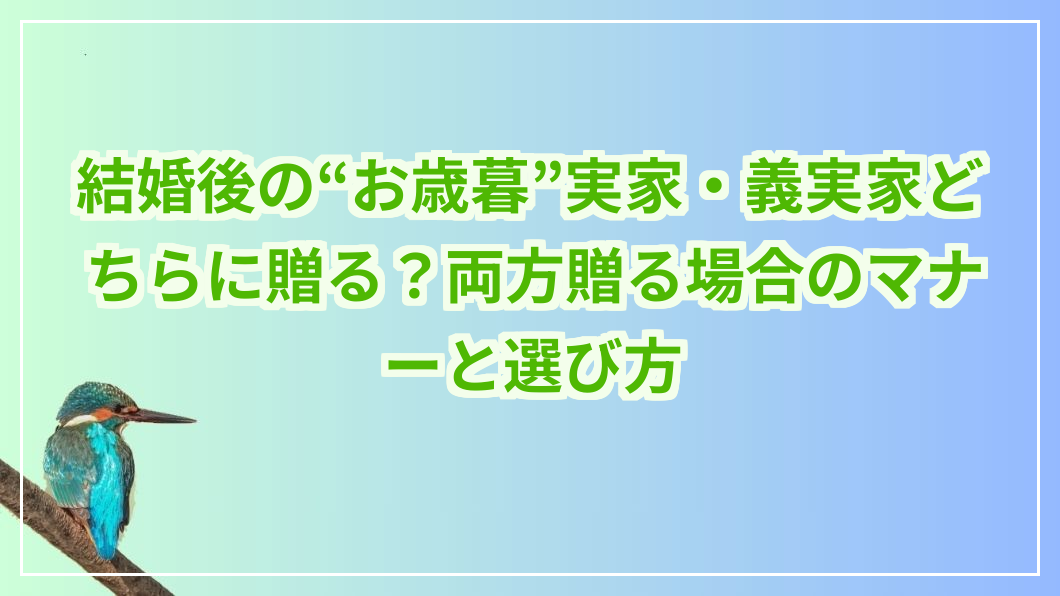結婚して初めて迎えるお歳暮の季節――「実家と義実家、どっちに贈ればいいの?」と頭を抱えていませんか?
実家には毎年贈っていたけれど、義実家にも贈るべき? それとも両方? 相場やマナーを調べても、家庭によって意見がバラバラで、ますます分からなくなるものですよね。特に、「片方だけにしたら失礼かな…」と悩む方は多いはずです。
でも大丈夫。お歳暮は“正解が一つではない”ギフトです。大切なのは、形式よりも「感謝の気持ちをどう伝えるか」。
この記事では、実家・義実家どちらに贈るべきか迷ったときの判断基準から、金額やおすすめギフト、そしてやめたいときの上手な伝え方まで、まるっと分かりやすく解説します。
読み終わるころには、「これなら自分たちらしく贈れる!」とスッキリした気持ちで年末を迎えられるはずです。
結婚後「実家・義実家どちらへお歳暮?」迷ったときの3つの判断基準
お歳暮の季節が近づくと、結婚後の夫婦にとって頭を悩ませるのが「実家と義実家、どちらに贈るべき?」という問題です。独身のときは実家だけで済んでいたのに、結婚後は“両方に贈らなきゃいけないの?”と戸惑う人も多いのではないでしょうか。ここでは、その判断をスッキリつけるための3つのポイントを紹介します。
なぜ“両方贈る”という選択が無難なのか
初めてのお歳暮シーズンでは、まず両方に贈るのが無難です。理由はシンプルで、どちらの家にも「気遣いを見せる」ことができるからです。特に義実家とはまだ距離感を探っている時期。お歳暮は“感謝の気持ち”を形で伝える絶好のチャンスになります。仮に、実家にだけ贈って義実家に贈らなかった場合、「うちは軽視されているのかしら?」と感じる義両親もいるため、最初のうちはトラブル防止の意味でも両方に贈るのがおすすめです。
実家だけ/義実家だけで済ませてもいいケースとは?
ただし、毎年続けていくとなると金銭的・心理的な負担が出てくるのも事実です。夫婦の間で「どちらか片方にだけ贈る」という選択をする家庭も少なくありません。例えば、義実家の方から「気を使わなくていいから」と言われている場合や、どちらかの親が明確に辞退している場合などは、無理に贈る必要はありません。ポイントは、“親の意向”と“夫婦の納得”のバランスを取ることです。
判断前に夫婦で確認しておくべきこと
お歳暮に関する価値観は家庭によって大きく異なります。そのため、まずは夫婦で話し合うことが何より大切です。どちらの家庭がどんな風習を持っているのか、どれくらいの頻度や金額で贈るのが適切なのかを擦り合わせておきましょう。後々「うちの親はこう思ってたのに」とトラブルになるのを防ぐことができます。
実家・義実家に贈る「お歳暮」の相場と贈る時期を知ろう
一般的な金額:3,000〜5,000円が目安な理由
お歳暮の相場は3,000円〜5,000円前後が一般的です。これは、「負担にならず、気持ちが伝わるちょうどよい価格帯」として定着しています。最初の年は5,000円程度でしっかりと感謝を表し、関係が安定してきたら4,000円前後に落ち着かせる家庭も多いです。高価すぎる品を贈ると、かえって相手に気を使わせてしまうこともあります。
贈る時期はいつまで?地域差とタイミングのポイント
お歳暮を贈る時期は、関東では12月上旬〜20日頃、関西では12月13日〜20日頃が一般的です。年末ギリギリになると配送が混み合い、到着が遅れることもあるため、早めの手配が安心です。もし直接渡す場合は、年末の帰省時やお正月の前に手渡しできるように調整しましょう。
金額を下げるのはNG?翌年の継続のための注意点
お歳暮は「感謝の気持ちを継続的に伝える行為」です。そのため、前年より明らかに金額を下げると「気持ちが薄れた」と感じられる可能性もあります。どうしても金額を抑えたいときは、金額を下げるよりも“質を変える”のがスマートです。例えば、量より質を重視したギフトや、季節限定の特別感ある商品を選ぶと好印象です。
暮らし方別に考える「贈るべきお歳暮の品物」選びのコツ
実家・義実家が夫婦2人暮らしならこれがおすすめ
ご両親が二人暮らしの場合、量よりも「質」や「日持ちの良さ」が重視されます。少量でも高品質なグルメギフトや、食べきりサイズの詰め合わせが喜ばれます。例えば、高級ハムセットや、少し贅沢な和菓子、上質なコーヒーギフトなどは定番です。
家族が集まる実家・義実家には“みんなでシェアできる”ギフトを
お盆や正月などに家族が集まる家庭では、複数人で楽しめるギフトがぴったりです。お菓子の詰め合わせ、鍋用のスープセット、果物など、家族全員で囲めるものは会話のきっかけにもなります。特に小さな子どもがいる家庭では、お菓子やジュースなどの“子どもウケ”も意識すると喜ばれます。
遠方に住むご両親へは“ご当地名産+配達”で差をつける
遠方に暮らす実家・義実家には、地元の名産品を贈るのも粋です。「今年はこちらの特産を送りました!」というメッセージを添えると、離れていても繋がりを感じられます。冷凍配送を活用して、美味しい状態で届けるのもおすすめです。
「片方だけ」「お歳暮をやめたい」場合のマナーと伝え方
一度始めたら簡単にやめられない理由
お歳暮は一度贈り始めると、毎年の“恒例行事”として定着しやすいものです。突然やめてしまうと、「どうして?」と疑問に思われる可能性もあります。感謝の気持ちが伝わらなくなるだけでなく、誤解を生むリスクもあるため、やめるときは慎重に。
不要・やめたいときのやさしい断り方・代替案
もし「もう贈らなくていい」と言われた場合や、自分たちの負担が大きいと感じる場合は、代わりに“お正月の手土産”など別の形で感謝を伝える方法があります。「気持ちは変わらずあります」と添えるだけでも、印象はぐっと柔らかくなります。
夫婦で決めた方針はきちんと両親に伝えよう
お歳暮の有無を決めた後は、どちらの親にも同じ温度感で伝えることが大切です。「話し合ってこう決めました」と、夫婦で一緒に伝えるのがベスト。片方にだけ伝えると、誤解や温度差が生じることがあります。
夫婦でスムーズに決める!お歳暮方針を立てるための3ステップ
ステップ1:夫婦で「どうしたいか」を話し合う
まずは「お歳暮を贈る目的」を夫婦で明確にしましょう。「形式として贈りたい」「感謝を伝えたい」「今後の関係を円滑にしたい」など、目的が定まると判断もスムーズになります。
ステップ2:各ご両親の好み・家族構成・習慣をチェック
両親の好みやライフスタイルを知ることも大切です。例えば、食事制限のある親にお菓子を贈るより、日用品やお茶を選んだ方が喜ばれるケースもあります。ちょっとした気遣いが「分かってくれている」と好印象に繋がります。
ステップ3:選んだ方針を両家に円滑に伝えるためのコツ
夫婦で話し合って決めた内容は、丁寧に伝えることが肝心です。メールや電話で一言「今年はこういう形にしました」と報告するだけでも安心感が生まれます。感謝の言葉を添えると、より温かい印象になります。
ケース別実践例+おすすめギフト3選でイメージ具体化
ケースA:実家・義実家ともに年末年始集まる大家族の場合
家族が多い家庭には、シェアしやすいお菓子やジュースセット、鍋の具材セットなどが最適です。みんなで囲めるギフトは「今年も楽しく過ごそう」という気持ちを伝えやすいですね。
ケースB:義実家遠方・2人暮らしの両親の場合
遠方の両親には、日持ちのする高級食品や、ご当地グルメを冷凍便で送るのがおすすめです。例えば「明太子」「うなぎ」「高級ハム」など、特別感がありつつ手間のかからないものが喜ばれます。
ケースC:交流が少なくお歳暮をやめたいと思っている場合
無理に贈り続ける必要はありません。「いつもありがとうございます。今年はお正月に改めてご挨拶に伺いますね」といったメッセージを添えて、別の形で感謝を伝えましょう。
各ケースでの「金額」「品物」「手渡し/宅配」のおすすめ
大家族には5,000円前後のシェア向けギフト、二人暮らしには3,000円前後の上質グルメを。手渡しができるなら季節感のある包装にこだわり、宅配なら“のし”とメッセージカードを忘れずに添えるのがポイントです。
まとめ:迷ったときはこれだけ覚えておけば安心
今日からできる一歩:夫婦で〇〇を決めよう
まずは夫婦で「どういう気持ちで贈りたいのか」を話し合うことから始めましょう。目的が定まると、金額や相手への伝え方も自然と見えてきます。
持っておきたい「やめる時のマナー」「翌年続ける時の注意」
一度贈り始めたお歳暮は、やめるときほど気を遣います。やめる場合は代わりの手土産や言葉を添えて、誠意を見せることが大切です。翌年も続けるなら、前年と同程度の金額や品質を維持することを意識しましょう。
年末、お歳暮を通じて「感謝の気持ち」を伝えるコツ
お歳暮は、義務ではなく“感謝を伝えるきっかけ”です。形式にとらわれすぎず、「ありがとう」の気持ちを素直に表すことが何よりも大切です。今年はちょっと気の利いたギフトで、心の距離をぐっと近づけてみてはいかがでしょうか。