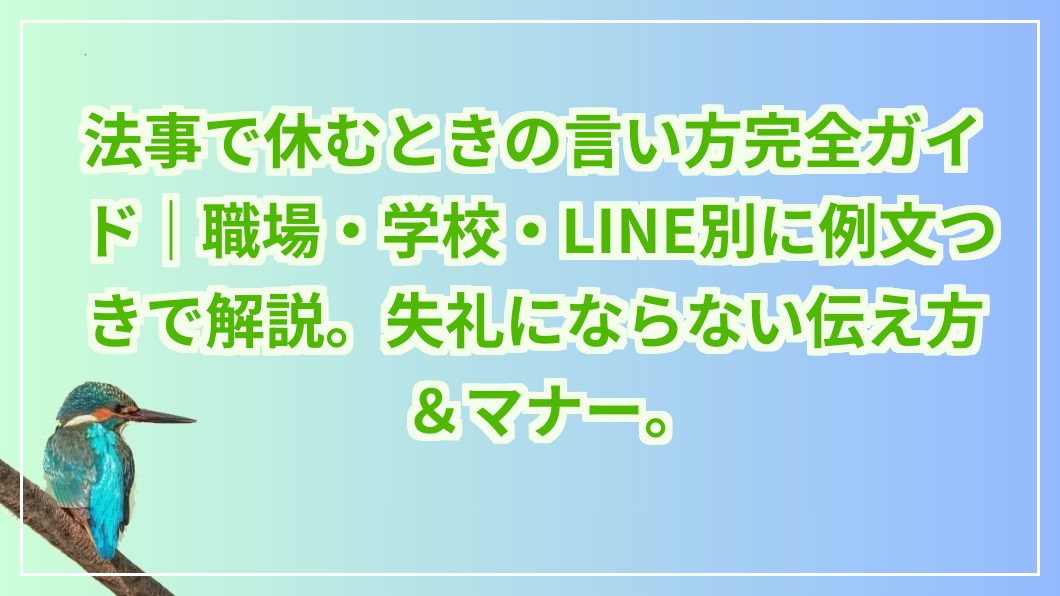「親族の法事でお休みしたい…でも、どう伝えれば失礼にならないの?」
職場や学校、習い事での“お休みの伝え方”って意外と悩みますよね。特に「法事」と聞くと、ちょっと堅苦しく感じて、言い方にも気を使いたくなるものです。
この記事では、「法事 休み 言い方」に迷うあなたへ、ビジネスシーン・学校・LINE・電話など場面別の言い回しと例文をわかりやすく解説。さらに、忌引きとの違いや、お休み後のフォロー文まで、好印象を残せるマナーのコツをまとめました!
「なんて言えばいいの?」という不安がなくなれば、もっと安心して休みを伝えられますよ✨
それでは詳しくご紹介していきますね!
法事で休むときの基本マナー
親族の法事でお休みを取る――決して珍しいことではないのに、「なんて伝えたらいいんだろう?」と迷う人は意外と多いんです。
まず覚えておきたいのは、「法事」という言葉自体はきちんとした理由として問題ないということ。
ただし、相手によっては宗教的な行事に関して踏み込みたくない場合もあるため、伝え方には少しだけ配慮が必要です。
基本マナーとして大切なのは、以下の3点です👇
- お休みの 事前連絡はなるべく早く(最低でも前日までに)
- 詳細を話しすぎず、必要最小限で簡潔に
- 感情を込めすぎず、あくまで落ち着いたトーンで
たとえば会社や先生への連絡では、「親族の法要のためお休みさせていただきます」と伝えると、丁寧かつ角の立たない印象になりますよ☺
「法事」と伝えても問題ない?
「法事ってそのまま言って大丈夫?」と心配になる気持ち、よくわかります。
でも実は、「法事」というワード自体に失礼な印象はありませんし、職場や公的な場でも使ってOKな表現なんです。
とはいえ、言葉の選び方は状況や相手との関係性によって変えるのが大人の気づかい。
✔ たとえば…
- 【職場】「法事のため、○日にお休みをいただきたく存じます。」
- 【学校や習い事】「親族の法事があるため、○日は欠席いたします。」
- 【カジュアルな場面】「身内の法要がありまして、お休みさせていただきます!」
「親族の用事」「家庭の事情」などに言い換えてもいいですが、かえって不自然に感じさせる場合もあるので注意が必要です。
不安なときは、「法事」とだけ伝え、詳細は語らないのが安心です♪
言い方のポイントと注意点
丁寧な言い方=かしこまった敬語を連ねること、ではありません。
法事のお休みを伝えるときに大切なのは、**相手への配慮と、情報の“引き算”**です。
✔ 気をつけたいポイント
- 法事の詳細(誰の法事・宗派など)は言わない
- 相手に余計な心配をかけない言い回しにする
- 「法事でお休みします」だけだとぶっきらぼう。一言お詫びやお礼を添えると好印象に!
たとえばこんな風に👇
「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」
「ご理解いただけますと幸いです」
ちょっとしたひと言で、グッと印象が柔らかくなるんです♪
ビジネスで使える言い方の例
仕事をお休みする場合、やはり社会人らしい表現と誠実さが求められますよね。
でも、「法事だから…」と気負う必要はありません。あくまで**“きちんと伝える”ことが目的**です。
上司や同僚に伝えるときは、次のような言い方が◎です👇
✔ ビジネスで使える表現例
- 「○月○日は親族の法事のため、休暇を取得させていただきます。」
- 「恐れ入りますが、法要に参列するため、お休みをいただきたく存じます。」
- 「ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。」
ここでのポイントは、感情を入れすぎず、淡々と伝えること。
あまり神妙になりすぎると、かえって相手が気を遣ってしまいます。
メールや口頭のどちらでも、「予定としての事務的連絡+お詫び」のセットで伝えるとスマートです♪
学校や習い事での伝え方のコツ
お子さんが学校や習い事をお休みする場合、保護者としては「どのくらい説明すればいいの?」と迷いがち。
でも安心してください、学校や教室側も“法事”は理解されやすい理由の一つです。
✔ 丁寧だけど気軽な言い方
- 「親族の法事があるため、○日は欠席させていただきます。」
- 「家庭の事情でお休みいたします。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
あえて「法事」と言わずに、「家庭の事情」と表現しても問題ありません。
ただ、何度も続く場合は、「親族の法事で」など理由を軽く添えた方が誤解を招きません。
LINEで伝える場合も、堅苦しくなりすぎず、簡潔&やわらかいトーンを心がけましょう☺
メールでの連絡例(上司・先生宛)
いざメールを書くとなると、「あれ、どんな件名にすればいいんだっけ?」と戸惑うことってありますよね。
ここでは、ビジネスと学校(または習い事)向けのメール例文をシーン別にご紹介します!
✔ 上司へのメール例
件名:○月○日の休暇取得について(山田)
お疲れ様です。山田です。
誠に恐れ入りますが、○月○日は親族の法事のため、休暇を取得させていただきたく存じます。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。✔ 先生・習い事教室へのメール例
件名:○月○日 欠席のご連絡(佐藤りく)
お世話になっております。佐藤りくの母です。
○月○日は親族の法事があり、レッスンをお休みさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。ポイントは、「件名・理由・丁寧な締めくくり」の3点セット。
丁寧でわかりやすいメールは、読む相手の負担も少なくなり、信頼にもつながります♪
LINEで伝えるときの注意点と文例
LINEで休みを伝えるのって、気軽な反面、“軽く見える”リスクもありますよね。
だからこそ、スタンプ多用や砕けすぎた言葉は避けて、やわらかく丁寧な文章を心がけるのがポイントです。
✔ LINEで使える例文(職場・習い事など共通)
「おはようございます。○○の母です。親族の法事のため、○月○日のレッスンはお休みさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
✔ 注意すべきポイント
- 絵文字やスタンプは基本控えめ(1つ程度ならOK)
- 敬語は崩さず、「お休みします」「よろしくお願いします」で締める
- 深夜や早朝の送信は避ける(9〜21時が目安)
LINEは便利ですが、相手の“温度”が読めないからこそ、誠実さが伝わる文章を意識したいですね♪
電話で伝える場合の一言
急ぎのときや、メール・LINEで連絡がつかないときには、やっぱり電話が確実。
でも、電話で「法事のため…」って伝えるのって、ちょっと緊張しますよね。
コツは、事務的に“サラッと”言うこと。
あまり感情的にならず、淡々と話す方がスマートに聞こえます。
✔ 電話での伝え方例
「お忙しいところ失礼します。○○の母です。○月○日は親族の法事があり、レッスンをお休みさせていただきます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
会話の流れで詳しく聞かれることがあっても、無理に話さず
「身内の法要がありまして…」くらいでOK。
“必要最低限+丁寧さ”が電話でも通じるコツです。
忌引きとの違いを理解しよう
「法事でお休みって、忌引きになるのかな?」と悩む方もいますが、実は法事=忌引きではありません。
忌引きは、亡くなってから一定期間における“喪に服すためのお休み”のこと。
一周忌や三回忌などの法事は、“忌引き休暇の対象外”とされるケースがほとんどです。
✔ 忌引きとの主な違い
| 項目 | 忌引き | 法事 |
|---|---|---|
| 対象時期 | 死亡直後〜一定期間 | 命日や一定周期の法要 |
| 休暇扱い | 忌引き休暇がある場合あり | 有給休暇や私用扱いが多い |
| 言い方の違い | 「忌引きのため…」 | 「法事のため…」 |
職場や学校に伝える際は、「忌引き」ではなく「法事」と正確に伝える方が◎。
混同しないことで、トラブルや誤解を防げますよ。
宗教や故人について聞かれたら?
「どなたの法事ですか?」「何回忌ですか?」と聞かれて、ドキッとしたことはありませんか?
そんな時は、無理に答えなくても大丈夫。 プライベートな内容なので、相手も悪気なく聞いていることがほとんどです。
もし回答する場合も、簡潔&さらっと伝えるのがベストです。
✔ 答えてもOKな例
「祖父の三回忌でして…」
「父方の法事で、ちょっと出席しないといけなくて」
一方で、「ちょっと身内のことで…」と濁す形でもまったく問題ありません。
必要なのは**“お休みの理由が正当である”という信頼感**で、詳細は伝える義務はありません♪
失礼にならない表現の選び方
「失礼がないように伝えたい…!」という気持ちはとても大切。
ただ、気を使いすぎて言い回しが回りくどくなってしまうと、逆にわかりづらくなることも。
大事なのは、シンプル+敬意ある言葉選びです。
✔ 避けたいNGワード例
- 「ちょっと用事で」←あいまいすぎて誤解を招く
- 「親の葬式で…」←急に重く聞こえる可能性あり
- 「どうせ法事なんで」←雑な印象を与える
✔ 印象の良いフレーズ
- 「親族の法事のため、お休みをいただきます」
- 「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」
言いすぎず、でも雑に聞こえない…その**絶妙な言葉のバランスが“信頼される伝え方”**になります♪
お休み後のフォローメッセージ
法事でお休みした後、何も言わずに通常運転に戻るのもアリですが…
一言「ありがとうございました」と伝えるだけで、人間関係がぐっと良くなるんです。
✔ 休み明けに使える例文
- 「先日はお休みをいただき、ありがとうございました」
- 「ご迷惑をおかけしました。今後ともよろしくお願いいたします」
- 「お休みいただき助かりました。ありがとうございました!」
とくに職場や習い事では、こういった**“ちょっとしたひと言”が信頼の積み重ね**になります。
LINEやメールでもOKなので、さらっと送っておきましょう♪
伝え方で信頼関係が深まる理由
実は、「法事でお休みします」という連絡ひとつでも、その人の印象ってけっこう左右されます。
なぜなら、社会や人間関係においては、“伝え方=人柄”と捉えられることが多いから。
丁寧に伝える人は、「この人はきちんとしてるな」「安心して任せられるな」と思ってもらいやすいですし、逆に雑な伝え方は誤解や不信感につながることも。
たかが連絡、されど連絡。
でもだからこそ、少しだけ心を込めた言葉選びが、思いやりとして伝わるんです。
ほんのひと言が、人との距離をグッと縮めてくれる。
そんな力が、挨拶や連絡にはあるんですよ♪
✅ まとめ文
法事でのお休み連絡は、ちょっとした気づかいと丁寧な表現だけで、相手にしっかり気持ちが伝わります。
この記事で紹介したポイントを振り返ると…
- 法事と伝えるのはOK!でも詳細は控えめに
- 相手に合わせて、メール・LINE・電話で柔軟に対応
- 丁寧だけど長すぎない、読みやすい文章が好印象
- お休み後にひと言お礼を添えると、信頼度がグッとUP
- 忌引きとの違いを理解して、正確な言い回しを選ぶ
「正しく伝える=気を使う」ではなく、「思いやりのある言葉を選ぶこと」が大切です。
少しの配慮で、相手との関係がよりスムーズになりますように😊
最後までご覧いただきありがとうございました。