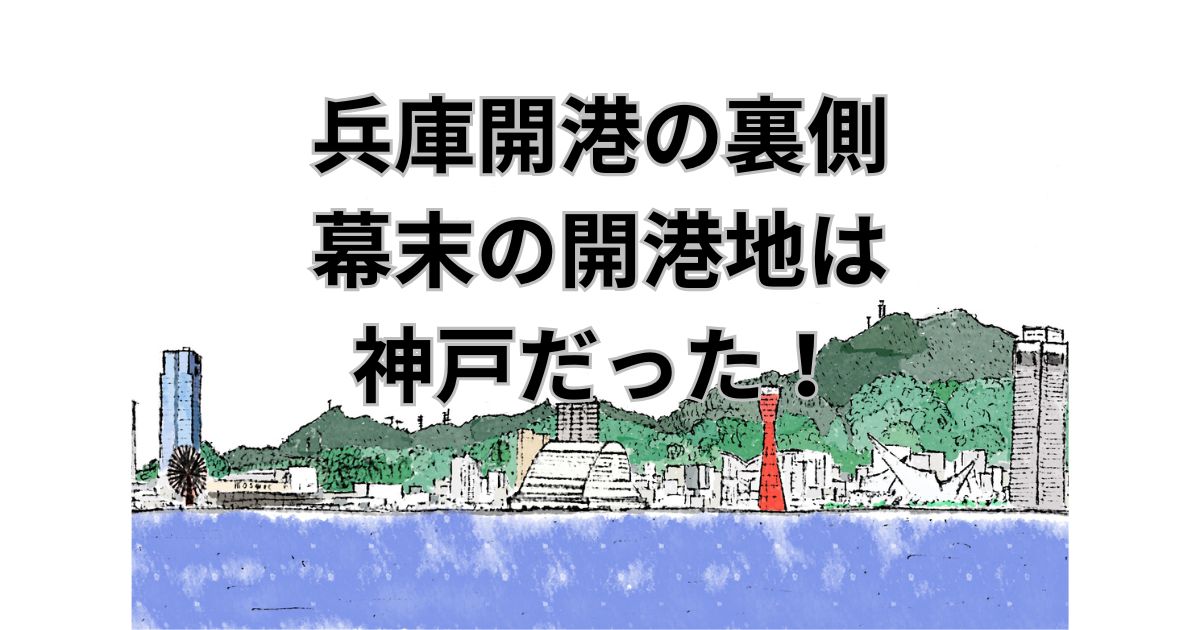幕末の日本において、1868年の「兵庫開港」は歴史的な転換点となりました。
しかし、ここで驚くべき事実があります。
私たちが一般的に「兵庫港」と呼ぶ場所が、実際には開港の舞台ではなかったのです。
開港が実際に行われたのは、兵庫津から約3.5キロ東に位置する神戸村。
なぜ、幕府は兵庫ではなく神戸を選んだのでしょうか?
その背景には、土地の条件や外交的な配慮、さらには外国人の意見が複雑に絡み合っています。
この記事では、この知られざる歴史の真相を紐解き、神戸がどのようにして日本の貿易の中心地へと成長していったのかを探ります。
あなたもこの歴史の裏側を知ることで、神戸の魅力を新たに発見できるかもしれません。
兵庫開港の背景
日本の歴史において、1868年1月1日に「兵庫開港」が宣言されたことは、特に重要な出来事とされています。
実際には、アメリカやイギリス、フランス、オランダ、ロシアと1858年(安政5年)に締結された「安政五カ国条約」において、開港場として「兵庫」が明記されていました。
しかし、実際に開港されたのは、兵庫津(港)(ひょうごのつ)から約3.5キロ東に位置する神戸村、つまり現在の神戸港だったのです。
開港場の変更理由
開港場の候補としての神戸村
神戸市文書館の歴史的資料によると、開港の前年である1867年の5月に、各国との間で「兵庫・大坂居留地に関する取極(とりきめ)」が結ばれた際に、開港場が神戸に変更されたことが記されています。
この取り決めの第一条には「居留地を神戸村と生田(いくた)川との間に取り決める」と明記されており、少なくとも開港の8カ月前には神戸村が開港場として決まっていたことがわかります。
兵庫の土地不足
では、なぜ兵庫津から神戸村に変更されたのでしょうか?
その理由はいくつか考えられます。
一つ目は、当時の兵庫はすでに人口が2万人を超える民家密集地帯であり、開港場に必要な施設を設置するための土地が不足していたことです。
しかし、これは表向きの理由に過ぎず、実際には兵庫に外国人居留地が建設されると、欧米の外交官や商人と地域住民との間でトラブルが生じる可能性が高かったため、幕府は外国人と日本人との接触をできるだけ減らそうとしたのではないかとも考えられます。
神戸村の地理的利点
二つ目の理由は、神戸村は当時、主に畑が広がる地域であり、外国人居留地を設けるには適した条件が整っていたことです。
このような土地の特性は、開港に向けた一つの利点とされました。
外国人の影響と提案
さらに、勝海舟(かつかいしゅう)の提案により設けられた神戸海軍操練所(1865年に廃校)の建物や、その付属施設である船入場(ふないりぱ)があったことも神戸村が選ばれる一因となったようです。
幕府はこれらの施設を有効に活用する考えがあったと推測されます。
加えて、外国人の専門家からもアドバイスがあったとされています。
1865年(慶応元年)に兵庫津の海域を測量したイギリス公使ハリー・パークスの随行員は、「兵庫から少し離れた場所にある予定地は十分な水深があり、天然の優れた投錨(とうびょう)地となっている小さな湾に面している」と記録しています。
この「兵庫から少し離れた場所」とは、まさに神戸村を指しており、この時点で神戸が開港場候補として考慮されていたことが伺えます。
パークスが幕府に対して「兵庫津よりも神戸村の方が開港場として適している」と進言し、幕府がその提案を承認したことが、神戸村への変更につながったのではないかという見方もあります。
しかし一方で、開港後も公文書には「兵庫居留地」と記されていたことから、多くの外国人が神戸村を兵庫津と誤解していた可能性も考えられます。
兵庫津の歴史
兵庫津について、もう少し詳しく見てみましょう。
もともと兵庫津は、高僧の行基(ぎょうき)によって天平年間(729〜49年)に開かれた五泊(5つの港)の一つ、大輪田泊(おおわだのとまり)として知られていました。
平安時代には平清盛(たいらのきよもり)によって大規模に修築され、鎌倉時代には「兵庫津」と呼ばれるようになり、周囲には町が形成されていきました。
この地域は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけて日宋(にっそう)貿易が盛んで、繁栄を見せていました。
応仁の乱によって一時衰退しましたが、江戸時代には西廻(にしまわり)航路の発達により再び活性化し、幕末の開港時には海上交通の要所として重要な役割を果たしていました。
神戸港の発展
しかし、神戸開港以降、神戸の港域が拡大され、兵庫津もその一部となりました。
その結果、明治政府は1892年(明治25年)に港の名称を「神戸港」と定めることになったのです。
このように「兵庫開港」とは、単に兵庫津を開港するのではなく、その東側に位置する神戸村に新しい貿易港を設けるという、画期的な都市開発の一環だったのです。
神戸の発展は、この歴史的な決定によって大きく進展したと言えるでしょう。
まとめ
1868年の「兵庫開港」は、日本の歴史において重要な出来事ですが、実際には兵庫港ではなく、神戸村が開港の舞台となりました。
この選択には、土地の条件や地域の特性、さらには幕府の外交的配慮が深く関わっています。
兵庫は当時すでに人口が密集しており、開港に必要な土地が不足していたため、より適した神戸が選ばれたのです。
また、外国人のアドバイスや勝海舟の提案も影響を与え、神戸が新たな貿易の中心地として発展する道が開かれました。
このように、神戸の港は単なる開港の場ではなく、幕末の日本が国際社会と接触する重要な拠点へと成長していったのです。
今日、神戸はその歴史を背景に、国際的な都市としての魅力を持ち続けています。
この歴史的な背景を知ることで、神戸の文化や風景をより深く理解し、楽しむことができるでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。