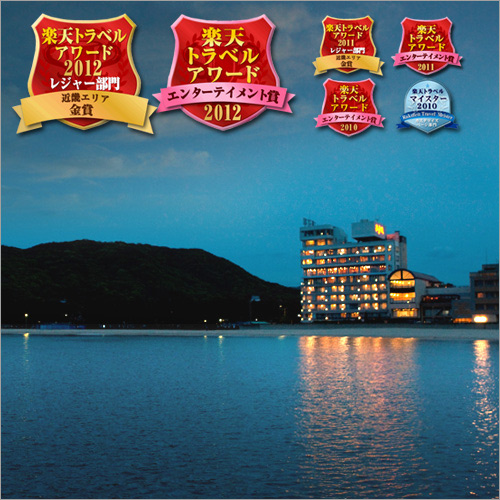日本列島の起源をめぐる壮大な物語、皆さんはご存知ですか?
遥か昔、海だけが広がる世界で、天の神々から国を生む使命を託された二柱の神がいました。
イザナギとイザナミ――彼らが海をかき混ぜたその瞬間、奇跡的に誕生したのが、私たちの住む日本列島。
その始まりを語る「国生み神話」は、ただの古い伝承ではなく、現代の私たちにも響く深い歴史と神秘に満ちています。
実際にこの神話の舞台がどこにあったのか、誰もが知りたいと思うことでしょう。
淡路島やその周辺に残る伝承に足を踏み入れると、古代の神々の息吹を感じられるかもしれません。
さて、この魅惑の世界へ一緒に旅してみませんか?
日本列島を生んだ神話のはじまり
古事記に記されている「国生み神話」は、日本の起源を語る興味深い神話の一つです。
昔、まだ陸地が存在しなかった時代、天上の神々は男神のイザナギと女神のイザナミに国を作るよう命じ、天の沼矛(あめのぬぼこ)という神聖な道具を授けました。
二神は天の浮橋からその矛を海に差し込み、かき混ぜると、矛の先から滴り落ちた水が積み重なり、最初の島が誕生しました。
この島が「オノコロ島」とされています。
オノコロ島の謎と伝説の場所
イザナギとイザナミはこの島に降り立ち、そこに柱を立て、神聖な御殿を建てました。
そして、二神はそこで結婚し、淡路島や四国、九州、本州など、日本列島を次々と生み出していったのです。
それでは、この神話の舞台であるオノコロ島は一体どこにあるのでしょうか?
実在するという説と、架空の島だという説が存在しますが、実在説を支持する人々は、淡路島近辺にその候補地を挙げています。
具体的には、南あわじ市の沼島(ぬしま)や淡路市の絵島、さらには和歌山市の友ヶ島がその候補地とされていますが、いずれも神話に深い関わりを持つ場所です。
南あわじ市の自凝島神社とその伝承
淡路島にあるオノコロ島関連の神社として有名なのが、自凝島(おのころじま)神社です。
この神社は南あわじ市の丘の上に立っており、そこには高さ21.7メートルの巨大な鳥居があります。
ここでは主にイザナギとイザナミを祀っており、その昔、この丘の場所は海上に浮かぶ島であったと伝えられています。
また、自凝島神社の近くには産宮(うぶみや)神社があり、ここのお砂所(すなどころ)には、天の沼矛から滴り落ちた海水が固まってできた塩砂が祀られています。
絵島と蛭子命の伝説
一方、淡路島の岩屋港にある絵島も、オノコロ島伝説に関連する場所です。
この近くには蛭子命(ひるこのみこと)を祀る岩樟(いわすく)神社があり、蛭子命が体に障害があったため海に流されたという話が古事記に記されています。
伝説では、蛭子命は流れ着いた先の西宮神社(現在の兵庫県西宮市)で祀られ、御神体となったとされています。
勾玉の形をした沼島と天の御柱
オノコロ島の候補地としてもう一つ挙げられるのが、沼島です。
沼島は空から見ると勾玉(まがたま)の形をしており、その海岸線には高さ30メートルの巨大な岩「上立神(かみたてがみ)岩」がそびえています。
この岩は、イザナギが天の沼矛でかき混ぜた際に固まったもの、またはその矛自体だとされ、天の御柱(あまのみばしら)とも呼ばれています。
さらに、この岩はイザナギの象徴とされ、その近くにある「下立神(しもたてがみ)岩」はイザナミの象徴とされています。
江戸時代の百科事典『和漢三才図会』では、上立神岩は竜宮城の表門に当たるとされています。このように、神話と地形がリンクする場所がいくつか存在するため、オノコロ島の伝承が色濃く残っているのです。
海人集団と国生み神話の伝承
現在、オノコロ島の候補地は複数ありますが、特に淡路島周辺が注目される理由は、古代から淡路島に住んでいた海人(あま)と呼ばれる人々が「国生み神話」を語り継いできたからだとされています。
彼らは漁業や海運、製塩などで生活を営みながら、神々への信仰を深め、特にイザナギとイザナミを祀る習慣が根付いていました。
このような信仰が、ヤマト王権との関係を深め、海人たちの伝承が大きな神話に発展していったと考えられています。
さいごに 淡路島と神話の魅力に触れる旅
日本列島の誕生を描く「国生み神話」は、古事記に記された壮大な物語です。
イザナギとイザナミがオノコロ島をはじめ、淡路島や四国、本州などを生み出したという伝承は、現代に至るまで多くの人々を魅了し続けています。
特に淡路島やその周辺には、この神話にまつわる場所が数多く残されており、神話の舞台とされる自凝島神社や沼島の伝説は、訪れる人々に深い感銘を与えます。
こうした神話と地元の伝承が結びつき、私たちに日本のルーツを感じさせる貴重な文化遺産となっています。
神話の世界に触れながら、淡路島を巡る旅は、歴史や文化、そして日本の成り立ちに対する新たな視点を提供してくれることでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。